骨折
膝の骨折
2020.08.11
膝関節周辺の骨折は、膝関節の機能である過重・安定機能にどれだけ影響を与えるかという観点で、その程度や後遺障害残存性を判断します。合併しやすい二次性変形性膝関節症と関節可動域制限は、労働能力のみならず日常生活動作にも影響を与えますので、膝関節周囲の骨折に対する治療は、まずこれらの二次性障害を予防する方法をとられることが多いです。
①大腿骨遠位部骨折
(1)概要
大腿骨の膝に近い部分を骨折した状態です。
大腿骨遠位部は、脛骨近位部、膝蓋骨とともに膝関節を構成します。

大腿骨の遠位部は、内側・外側顆上部、顆部へと移行し、顆部前面は膝蓋骨と大腿膝蓋関節を構成します。遠位端部は内側・外側顆に分かれ、両顆間部は深く陥没し顆間窩を構成し、その底部側面は前・後十字靭帯の起始部となります。大腿骨内側・外側顆には、それぞれ内側側副靭帯、概則側副靭帯が付着しています。
一方で、大腿骨顆部関節面は2つの球状をなし、脛骨関節面と大腿脛骨関節を形成します。この関節は、骨形態的に不適合なため、靭帯半月板などにより静的安定性を保っています。
以上の解剖学を理解することにより、大腿骨遠位部を受傷した場合、併発する周辺組織の損傷は何か、どの程度膝関節の機能が障害されるかを予想することができます。
(2)症状
骨折部の疼痛、腫脹、起立・歩行困難、膝関節可動域制限
(3)認定されうる後遺障害等級
疼痛等感覚障害の後遺障害等級である14級9号ないし12級13号のほか、以下の等級該当性がある。
| 後遺障害等級第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害等級第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害等級第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(4)診断
ア 臨床所見
明らかな受傷機転に加え、歩行困難、局所の疼痛、腫脹、肢位異常や変形、異常可動性などの臨床所見によって診断されます。
イ レントゲン
2方向撮影、さらには必要に応じて斜位像を含めたレントゲン撮影によって骨折形態が明らかになります。
ウ CTないしは3DCT
関節内骨折の場合には、関節内の骨片などの有無や転位の程度を確認するため、レントゲン撮影に加えてCTないしは3DCTを撮影する必要があります。
エ MRI
靱帯損傷、半月板損傷、不顕性骨折や軟骨骨折の確認のために、強度の疼痛がある場合や膝部に不安定性が認められる場合などは、MRIを主治医に作成してもらいましょう。
(5)評価の視点
後遺障害等級評価の視点は、以下のとおりです。
①骨折線が、関節内に達するような骨折か否か
骨折線が関節内に達しない骨折(関節外骨折)であれば、後遺障害が残りにくいとされているし、残ったとしても後遺障害等級は14級9号が認定されるにとどまることが多いです。
②骨折の転位があるか
転位のある骨折は、周辺の軟部組織を傷つけている可能性があり、また、完全な整復が困難なため、症状が残りやすいと評価できます。
③症状固定時に関節面の不整が認められるか
症状固定時に関節面の不整が認められなければ、後遺障害等級12級13級以上の可能性は高くありません。関節面に不整が認められるからこそ、痛みが立証されていると考えられています。
なお、症状固定時に関節面の不整が認められるかを確認するためには、レントゲンでは不十分(見えにくい)なので、CT撮影をお勧めします。
②脛骨近位端部骨折(プラトー骨折)
(1)概要
脛骨(すねの骨)の膝に近い部分を骨折した状態です。
脛骨顆部は大腿骨顆部とともに大きな可動域を有する大腿脛骨関節を構成し、その形態上の特徴と大きな荷重や外力が加わりやすいこと、さらには両骨は強靭な靱帯により固定されていることから、複雑な骨折を生じやすいとされています。
これらの骨折により、関節面の不適合や下肢軸の異常をきたすと、膝関節としての大きな機能障害が惹起され招待変形性関節症に発展することが多いとされています。
(2)症状
骨折部の疼痛、腫脹、起立・歩行困難、膝関節可動域制限
(3)認定されうる後遺障害等級
疼痛等感覚障害の後遺障害等級である14級9号ないしは12級13号のほか以下の等級該当可能性がある。
| 後遺障害等級第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害等級第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害等級第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(4)診断
ア レントゲン
膝関節正面像、側面像の2方向撮影によって行われますが、脛骨関節面は後方に9~13度傾斜しているために、通常撮影される正面像ではdepression型骨折による関節面の変形を正確に把握できないことが少なくないとされています。関節面の陥没の程度は、関節面の正常部分、または対側関節面の高位を基準として診断します。
イ CT・MRI
CT、MRIでは水平面横断像も見ることができるので関節面に広がる転位bursting、陥没部位などの多くの情報が得られます。MRIは半月板、靱帯損傷などの合併損傷、特に三次元CT像は膝関節をいずれの方向からも立体的に観察することができるので正確な診断、治療計画をたてるうえで極めて有用になります。
ウ 関節鏡
関節鏡による直視下に関節面の損傷程度のみならず半月板、靱帯損傷の有無を診断することができます。
(5)評価の視点
後遺障害等級評価の視点は、以下のとおりです。
①骨折線が、関節内に達するような骨折か否か
骨折線が関節内に達しない骨折(関節外骨折)であれば、後遺障害が残りにくいとされているし、残ったとしても後遺障害等級は14級9号が認定されるにとどまることが多いです。
②骨折の転位があるか
転位のある骨折は、周辺の軟部組織を傷つけている可能性があり、また、完全な整復が困難なため、症状が残りやすいと評価できます。
③症状固定時に関節面の不整が認められるか
症状固定時に関節面の不整が認められなければ、後遺障害等級12級13級以上の可能性は高くありません。関節面に不整が認められるからこそ、痛みが立証されていると考えられています。
なお、症状固定時に関節面の不整が認められるかを確認するためには、レントゲンでは不十分(見えにくい)ので、CT撮影をお勧めします。
③膝蓋骨骨折
(1)概要
膝の皿部分を骨折した状態です。直達外力または介達外力により発生しますが、粉砕骨折は直達外力、横骨折は介達外力によると考えられています。骨折片の大部分が軟骨のため、レントゲン写真では描出されにくいなどの特殊性があります。
(2)症状
関節血症による著名な腫脹、局所の局限性圧痛、膝関節運動の可動域制限、軋音
(3)認定されうる後遺障害等級
| 後遺障害等級第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 後遺障害等級第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
(4)診断
ア 臨床所見
局所の疼痛、関節血症(腫脹)、膝関節自動完全伸展障害などの臨床所見がみられます。亀裂骨折の場合は、打撲などとの鑑別が必要になります。
イ レントゲン
通常の2方向撮影(膝蓋骨正面撮影と膝関節正面撮影とは異なります。)に、もし膝関節屈曲が可能であれば軸写像を撮影します。分裂膝関節との鑑別診断が重要ですが、分裂膝関節は膝蓋骨の上外側にみられ関節血種を伴わないので、この視点で鑑別が必要となります。
ウ CT・MRI・関節鏡
骨軟骨骨折の場合は、レントゲン画像上、骨片が造影されないことがあります。そのため、CTやMRIのほか、直視下で観察できる関節鏡検査は確定診断にきわめて有用であるとされています。
(5)評価の視点
後遺障害等級評価の視点は、以下のとおりです。
①複雑性の骨折か否か
膝蓋骨は膝関節を形成するものではありますが、大腿骨遠位部や脛骨腓骨近位部と比べて関節の可動を直接構成しません。しかし、単純骨折の場合には整復さえすれば可動域は回復しますが、複雑性の骨折の場合には、骨片が関節内に入り込む可能性もあり、膝関節の可動域制限を直接推認させます。
②骨折の転位があるか
高度な転位があれば、①と同様の理由から、骨片が膝関節の可動域制限の原因となったり、周辺の組織を傷つけている可能性があります。
③症状固定時に関節面の不整が認められるか
症状固定時に関節面の不整が認められなければ、後遺障害等級12級13級以上の可能性は高くありません。関節面に不整が認められるからこそ、痛みが立証されていると考えられています。
なお、症状固定時に関節面の不整が認められるかを確認するためには、レントゲンでは不十分(見えにくい)ので、CT撮影をお勧めします。
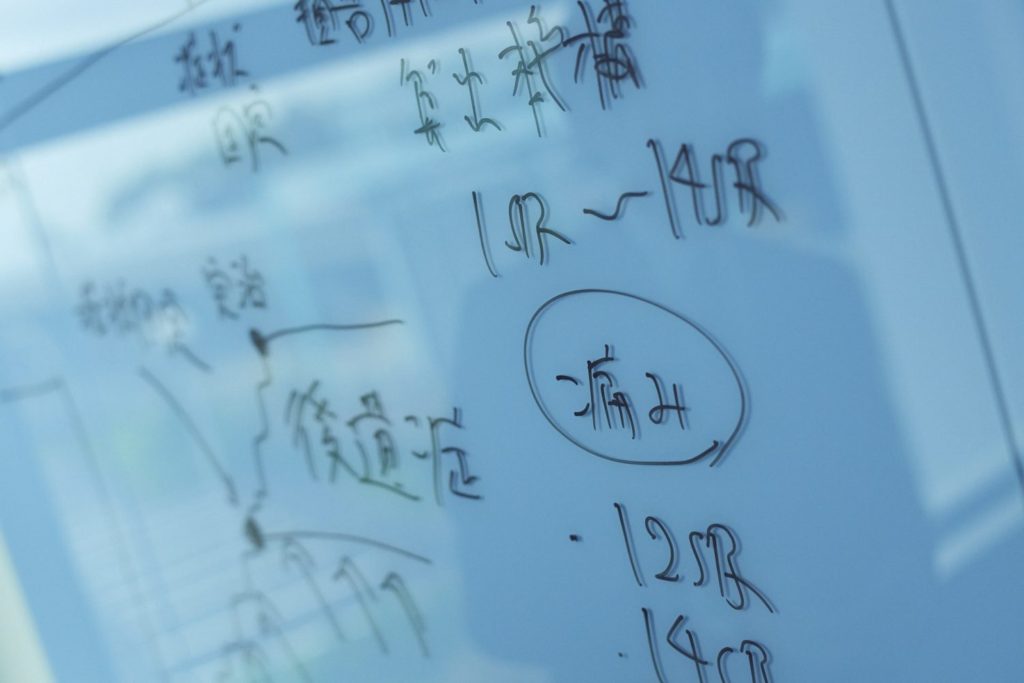
 弁護士
弁護士