後遺障害14級に該当する後遺症が残った時の逸失利益は?【弁護士解説】
2024.11.19
損害賠償請求
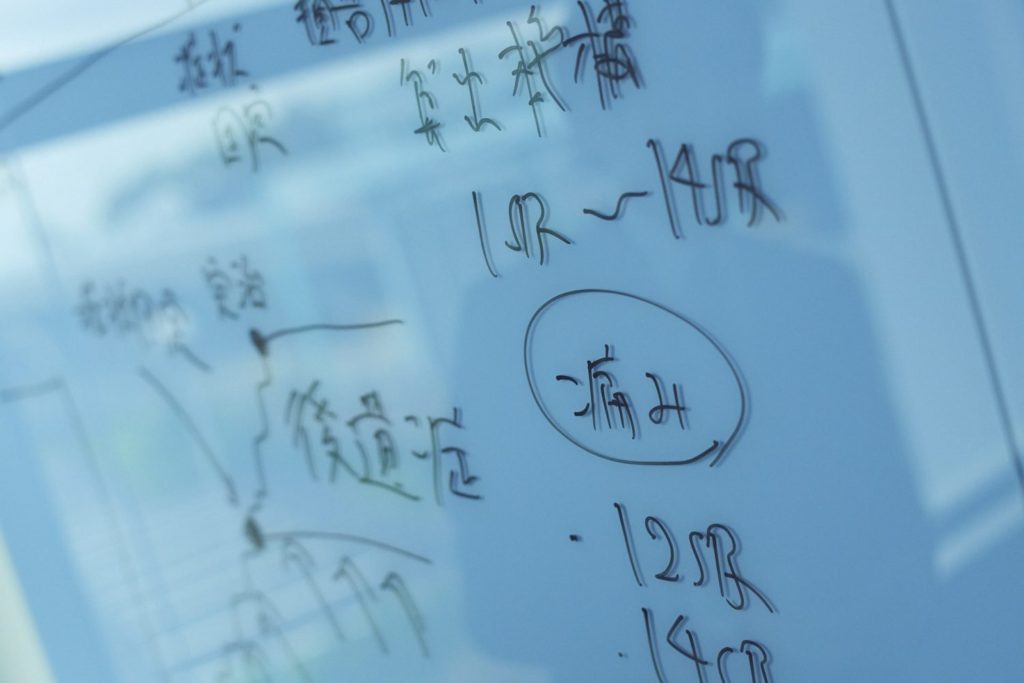
事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合には、
将来にわたって働きにくさが残ってしまうという損害が発生します。
将来にわたって働きにくさが残り、本来であれば得られるはずであったのに得られなくなった利益のことを、
逸失利益といいますが、その逸失利益の額は様々な要因で変化します。
今回は「後遺障害14級」に該当するような後遺症が残存した場合に、
逸失利益がどのように計算されるかを後遺症被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。
後遺障害14級の認定を受け、逸失利益の額が妥当が疑問に思われている方は、
ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
後遺障害14級とは?

後遺障害14級とは、自賠責保険や労災保険、スポーツ振興センター等で認定される後遺障害等級のうち、最も低い等級になります。
後遺障害等級の認定を受けることで、逸失利益や、後遺症慰謝料などの費目の請求が可能になるわけですが、
実務上は認定される等級に応じて画一的に金額が決定されることも多いです。
つまり、後遺障害14級が最も低い等級であるということは、支払われる金額も最も低くなります。
したがって、そもそも異議申立てなどの手段によって認定された後遺障害等級を上げるということ自体が、
損害賠償金の額を上げることに大きくつながるわけですが、
ここではひとまず後遺障害14級が認定された場合の逸失利益の計算についてみていきましょう。
後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』に記載がある、
| 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) |
を用いることが実務上の原則といえます。
一応「逸失利益の算定は労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う。」
とされていますが、示談交渉の段階でここを大いに争うことはあまりありません。
基礎収入
基礎収入は、原則として事故前の現実収入をいいます。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までとされています。
ただし、症状固定時から67歳までの年数が、平均余命の2分の1より短くなる場合は平均余命の2分の1としたり、
事故時18歳未満の人については18歳(または22歳)から計算するなどのルールもあります。
そして、認定された後遺障害等級が14級であった場合は、
実際の67歳までの期間の年数にかかわらず、労働能力喪失期間を3~5年程度に制限する運用が見られます。
これは、もともとむち打ち症で14級(14級9号 14級の9など)が認定された場合に、相当期間の経過による馴化、
一言でいえば後遺症が残っている状態に慣れて生活ができるようになることを考慮したものでした。
しかし、後遺障害14級=労働能力喪失期間は5年としてくる保険会社も多いように思われます。
ライプニッツ係数
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、中間利息の控除のための係数です。
逸失利益が後遺症が残ってしまったことにより本来得られるはずであったのに得られなくなった損害であるとすると、
損害賠償金の支払は解決時にまとめて一時金として支払われるのが原則ですから、
将来少しずつもらうはずだったものをまとめて今もらうことになります。
それを資産運用すると利息が付いてしまい、結果として事故に遭わなかった時より得をしてしまうので、利息分を差し引くために係数をかけるというわけです。
労働能力喪失率
最後見るのが労働能力喪失率です。
この労働能力喪失率は文字のとおり労働の能力を喪失した率ということになります。
この労働能力喪失率が、日本の実務においては認定された後遺障害等級に応じて画一的に決定される運用が圧倒的に多いです。
後遺障害等級と労働能力喪失率の関係については、
労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表にまとめられていて、
後遺障害14級に該当する後遺症が残存した場合の労働能力喪失率は5%とされています。
例えば事故前の年収が500万円で、症状固定時30歳の人がいたとすると、
この人に後遺障害14級が認定された場合の逸失利益は、
500万円×5%×22.1672(30年に対応するライプニッツ係数)=554万1800円となります。
ただし、これは弁護士基準による計算です。
以下では後遺障害14級が認定された場合の、
自賠責保険、労災保険、スポーツ振興センターにおける逸失利益の算定基準を見ていきましょう。
自賠責保険における逸失利益の算定基準

自賠責保険における逸失利益の算定基準は、基本的には弁護士基準と同じです。
つまり、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で計算されます。
ただし、自賠責保険は認定された後遺障害等級によって支払われる上限額が決まっています。
自賠責保険において後遺障害第14級が認定された場合の上限額は75万円です。
しかもこれは後遺症慰謝料と合わせた金額です。自賠責保険において後遺障害第14級が認定された場合の後遺症慰謝料は32万円ですから、
逸失利益はどれだけ基礎収入が高くても、どれだけ労働能力喪失期間が長くても、最大で43万円しか認められません。
交通事故において自賠責基準が最低限度の基準といわれる所以です。
労働者災害補償保険(労災保険)における逸失利益の算定基準
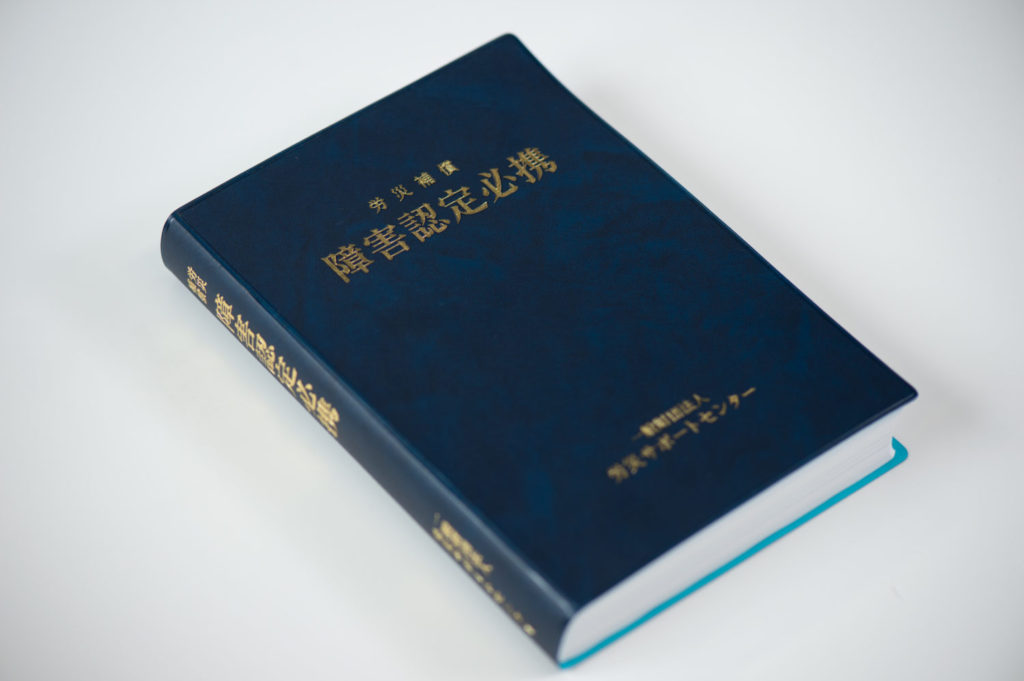
労災の場合はどうでしょうか。
労災の場合に後遺障害を認定してくれるのは労働者災害補償保険法(労災保険)です。
ただし、労災保険における後遺障害の認定はあくまで障害(補償)給付の支払のためです。
後遺障害14級が認定された場合には、障害(補償)給付として、
給付基礎日額の56日分の障害(補償)一時金と、8万円の障害特別支給金が支払われます。
給付基礎日額は原則として事故前3か月間の総収入÷総日数で算出されます。
労災保険は加害者がいない場合でも支払がある、労働者保護に資する保険なので致し方ないですが、やはり低額になります。
スポーツ振興センターにおける逸失利益の算定基準

通学中や学校で発生した事故について後遺障害を認定してくれるのはスポーツ振興センターです。
スポーツ振興センターも労災保険と同じように、障害見舞金の支払のために後遺障害を認定します。
後遺障害14級が認定された場合には、障害見舞金として88万円(通学中の場合は44万円)の支払があります。
自賠責保険よりは高額ですが、お子様のお身体に後遺症が残ってしまったということを踏まえればやはり低額です。
弁護士に依頼した場合の逸失利益の算定基準
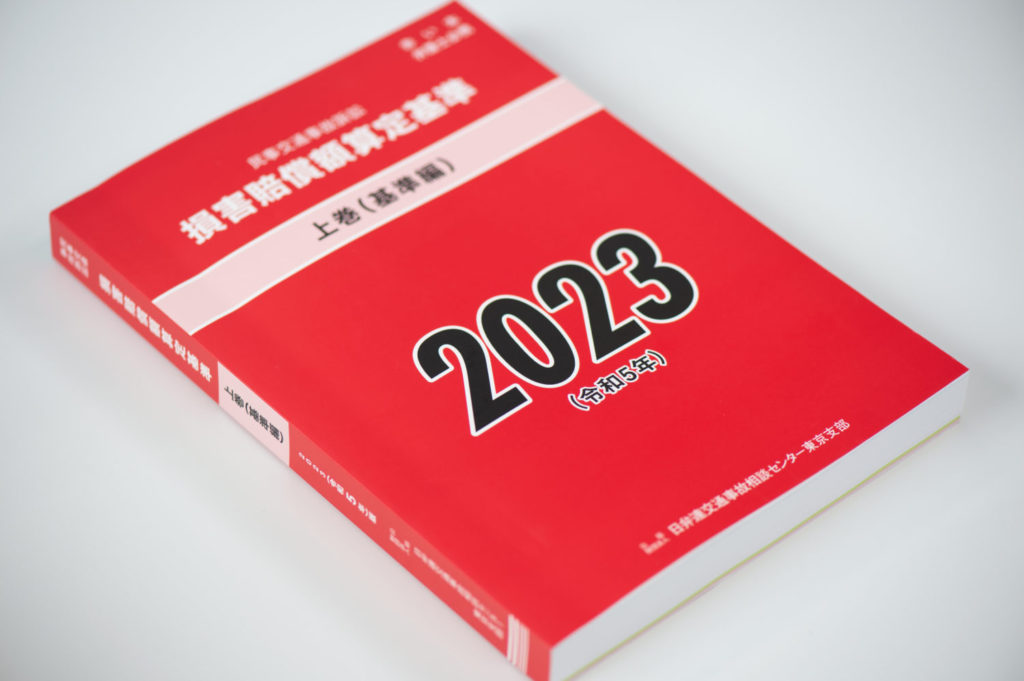
交通事故ではほとんどの場合で、労災や学校事故は相手方に損害賠償請求をしたような場合では、
加害者側が付帯していた任意保険会社との示談交渉が行われる場合があります。
任意保険会社はそれぞれの基準に少し色を付けた程度の提示しかしてきません。
したがって、弁護士に依頼し、弁護士基準をしっかり主張してもらうことで、逸失利益の額は大きく増額できる可能性があります。
しかし、後遺症被害に詳しい弁護士でなければ、画一的に基準にあてはめ、労働能力喪失期間は5年ほどで示談が終了してしまうかもしれません。
後遺症被害者専門弁護士に依頼した場合の逸失利益の算定基準

後遺症被害者専門弁護士に依頼した場合はどうでしょうか。
第一に、より上位の後遺障害等級の認定可能性がないかを検討し、異議申立てなどで上位の等級の認定に努めます。
そして、後遺障害14級のまま逸失利益の請求をする場合でも、
被害者の方一人ひとりの職業や、後遺症の部位、事故前と事故後の比較を丁寧に調査して5%以上の労働能力喪失率を認めさせるよう努めたり、
簡単に労働能力喪失期間を5年と制限させしないように努めたりします。
被害者の方一人ひとりに適切な逸失利益を認めさせるためには、経験や知識が必要不可欠です。
後遺障害14級が認定され、逸失利益の額が妥当かお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

 弁護士
弁護士
