死亡逸失利益計算における【生活費控除率】とは?被害者専門弁護士が解説!
2024.07.01
損害賠償請求

事故により被害者の方が亡くなってしまった場合、死亡逸失利益と呼ばれるものを請求できる場合があります。
「生活費控除率」は、その死亡逸失利益の計算において重要な役割を果たしています。
- 「生活費控除率」の意味は?
- 死亡逸失利益の計算にどのような影響があるのか?
- 「生活費控除率」の決定方法は?
- 弁護士に依頼するメリットはあるのか?
といった疑問について、被害者側専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側専門弁護士による無料相談を実施しています。
生活費控除率とは?
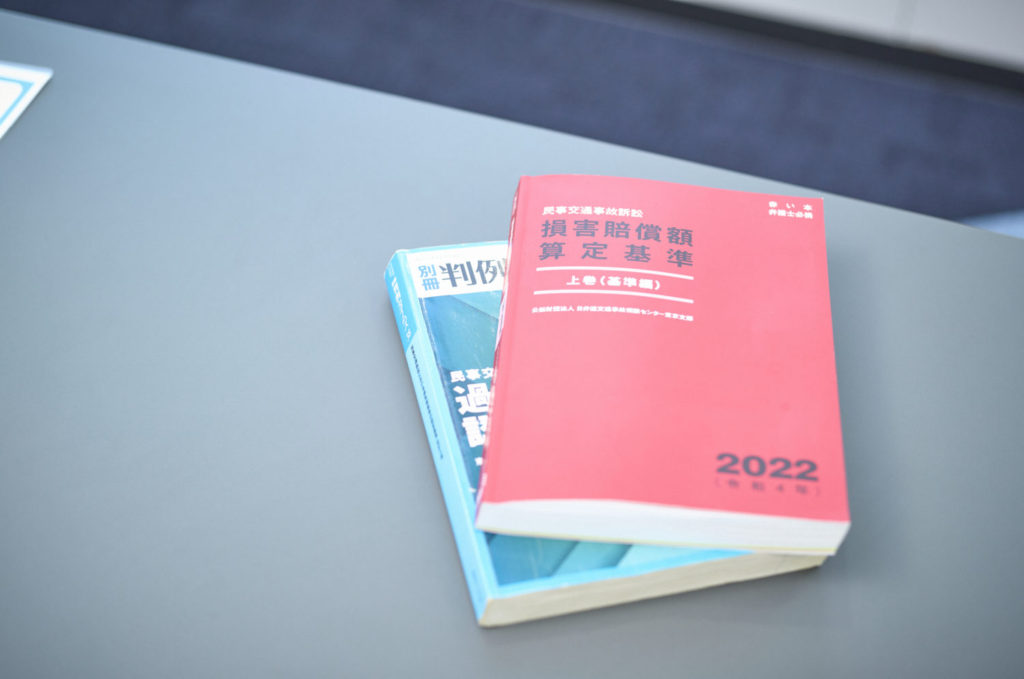
生活費控除率とは、読んで字のとおり、死亡逸失利益の計算において生活費を控除する割合です。
逸失利益とは簡単に言えば、事故に遭ってしまったことにより本来得られるはずであったのに得られなくなった収入のことですから、
「事故前の年収×事故後働くはずだった年数」が最も原始的な計算方法になるはずです。
ところが、事故により被害者が死亡してしまうような死亡事故の場合は、
事故に遭わなければ本来消費していたはずの生活費も、今後消費しなくなるということになります。
これを考慮せずに逸失利益を計算してしまうと、実態に則しておらず、被害者側が少なくとも金銭の面だけみれば得をしているという話になる可能性があります。
最高裁判所第三小法廷昭和43年8月27日判決(民事判例集第22巻8号1704頁)では、
「不法行為によつて死亡した者の得べかりし利益(当ページ執筆者注:死亡逸失利益のこと)を喪失したことによる損害の額を認定するにあたつては、
裁判所はあらゆる証拠資料を総合し、経験則を活用して、でき得る限り蓋然性のある額を算出するように努めるべきであり、蓋然性に疑いがある場合には
被害者側にとつて控え目な算定方法を採用すべきである」とされています。
その被害者の方が、事故に遭わずに寿命を全うしていたらどうなっていたかを、綿密に想像する必要があるわけです。
ここに、被害者側専門弁護士に依頼するメリットが隠されているのですが、その理由は後述します。
まとめると、生活費控除率とは、被害者が事故に遭わなければ費消していたであろう生活費を、死亡逸失利益の計算の際に控除するための率ということになります。
以上のような考え方を踏まえ、死亡逸失利益の計算は次のような式にあてはめて行われます。
死亡逸失利益=被害者の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数)
では実際に、生活費控除率が死亡逸失利益の計算にどのような影響を与えるのかについてみてみましょう。
生活費控除率が死亡逸失利益の計算に与える影響

先ほど見たように、死亡逸失利益の計算式は、
死亡逸失利益=被害者の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(に対応するライプニッツ係数)
です。
例として、被害者の基礎収入を500万円、就労可能年数を30年として計算します(ライプニッツ係数についてはここでは考慮しません。)。
例:基礎収入500万円 就労可能年数が30年 生活費控除率が30%の場合
生活費控除率が30%ということは、この被害者の方は自身の収入のうち30%を生活費に充てていたということになります。
この方の死亡逸失利益は、
500万円×(1-0.3)×30年=1億0500万円
となります。
例:基礎収入500万円 就労可能年数が30年 生活費控除率が50%の場合
次に、生活費控除率が50%の被害者の方についてみてみましょう。
この方の死亡逸失利益は、
500万円×(1-0.5)×30年=7500万円
となります。
このように生活費控除率が高くなれば死亡逸失利益の額は低くなり、
生活費控除率が低くなれば死亡逸失利益の額は高くなるという関係性にあります。
つまり死亡逸失利益の額を高くするためには、生活費控除率をできるだけ低く主張し、認めてもらうことが重要になるわけです。
では生活費控除率はどうやって決定されるのでしょうか?
生活費控除率の決定方法

生活費控除率の決定方法の大原則は、やはり生前の被害者の生活スタイルの反映です。
損害賠償請求実務において一般に支持されている、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』では、
「扶養」という点を前提に基準が設定されています。
被害者が誰かを扶養していた場合、収入の一部を自身だけでなく、その被扶養者の生活費にも充てていたはずです。
ということは、必然的に被扶養者がいない方に比べると、収入のうち、自身の生活費に充てていた額(割合)は小さくなるはずです。
といった考え方を前提に、原則的に設定されている生活費控除率は以下のようになります。
| 男性(独身、幼児等を含む) | 生活費控除率50% |
| 被扶養者が1人の一家の支柱 | 生活費控除率40% |
| 被扶養者が2人の一家の支柱 | 生活費控除率30% |
| 女性(主婦・独身・幼児等を含む) | 生活費控除率30% |
男性(独身、幼児等を含む)から、被扶養者が1人増えるごとに生活費控除率が10%ずつ減っているのは、
収入のうち自身の生活のみに充てられる額(割合)が減少するからです。
では、なぜ女性(主婦・独身・幼児等を含む)の生活費控除率が30%となっているかというと、
女性は将来的に家庭を持ち、男性の扶養に入ることが前提とされた基準だからです。
男性の扶養に入れば、例え共働きを継続した場合であっても、自身の収入のうち自身の生活にのみ充てる金額は小さくなります(男性が自身の生活分を払ってくれるため。)。
ですから、女性は将来も含め、男性の扶養に入ることを前提として生活費控除率が設定されています。
ですが、この基準はかなり前時代的です。
現在は女性の社会進出に伴い男性の扶養に入らずとも生活費を賄うことができる女性も大勢いらっしゃいますし、
そもそも性別で生活費控除率を区分していること自体が古い考え方です。
生活費控除率という考え方が出てきたのは、
死亡事故被害者の方が、事故に遭わずに生きていたらどのように生きていたかというifのストーリーについて、
可能な限り実態に則した計算をするためでした。
社会情勢に合わせた基準の変化も必要かもしれません。
(この死亡逸失利益における男女の問題に関して詳しく解説したページもございますので、ぜひご覧ください。
【弁護士解説】死亡事故被害者への最新の賠償金相場からみる男女差別
なぜ「死亡」逸失利益の場合にしか生活費控除率は考慮しないのか?
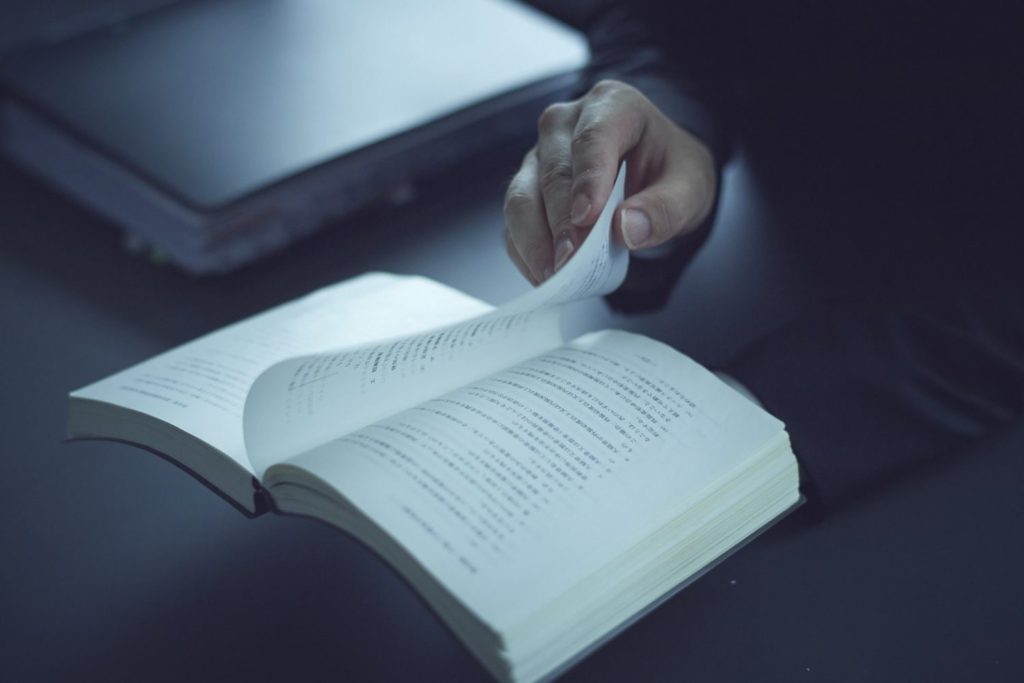
ところで、生活費控除率は、なぜ「死亡」逸失利益の場合にしか考慮されないのでしょうか。
事故により本来得られるはずだった収入が得られなくなったというのは、なにも被害者の方が亡くなった場合に限定されません。
事故により後遺障害が残り、労働能力を喪失してしまった場合も同様です。
ですが、後遺障害の逸失利益の計算においては生活費控除率は原則として考慮しません。
それには次のような理由があります。
生存している被害者は生活費を当然に支出する
後遺障害の逸失利益の計算において生活費控除率を原則として考慮しない理由はこれに尽きます。
死亡事故被害者と異なり、後遺障害が残っている被害者の方は生きており、当然に生活費を今後も支出するからです。
生活費控除率は、死亡事故の被害者について今後の生活費が発生しなくなった点について、実態に則したものにするために計算式に入れられるものでした。
今後の生活費が発生する後遺障害が残っている被害者の方の逸失利益の計算には必要ありません。
弁護士に依頼するメリットとは?

ここまでみてきたように、生活費控除率は、事故により死亡してしまった方の逸失利益の計算において、
その方が事故に遭わずに生きていた場合を想像し、可能な限り実態に則した金額を算出するために重要な役割を果たしています。
ですが、被扶養者の数によって区分けされた生活費控除率が、果たして可能な限り実態に則しているといえるでしょうか?
- うちの主人は節約家で、自身の生活にはあまりお金を使っていなかった。
- 事故時付き合っていた彼女と将来的に結婚して養っていくはずだった。
- 預金や資産が多かったので、収入を生活費に回す割合は少なかった。
といった被害者の方々それぞれに固有の事情があるはずです。
生活費控除率は死亡逸失利益の額に大きな影響を与えます。
少しでも生活費控除率を下げるためには、そういった固有の事情を的確に主張し、相手方や裁判所に認めてもらうことが必要になるのです。
ここに、弁護士に依頼するメリットがあります。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側専門の弁護士として、
そういった固有の事情をご家族の方々から正確に聞き取り、必要な証拠を集め、主張に適切に反映していきます。
死亡逸失利益は、亡くなった方がご家族の方の今後の生活のために遺されるものです。
それが、不適切な金額であってはなりません。
被害者の方が事故に遭わずに生きておられたらどのような将来を歩まれていたかを想像し、
それを適切に反映していくことが最も大切です。
お困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
死亡逸失利益の生活費控除率に関する解決実績の一例

上記説明のとおり、独身男性というのは生活費控除率が50%という最も高い水準で控除されてしまいます。
ですが、生活状況を細かく伝えていくことで、40%水準の生活費控除率として認定されることもありますし、独身男性であっても最高水準の30%の生活費控除率が認定されることもあります。
独身男性であるが生活費控除率30%で死亡逸失利益を認めさせた解決事例
独身男性(子どもも無し)であるが彼女の陳述書を元に生活費控除率40%で死亡逸失利益を認めさせた解決事例
また、高齢者は仕事をしていないことが多いので、年金収入のほとんどは生活費として費消されるという前提で死亡逸失利益の判断がなされることが多いです。
具体的には、年金収入の生活費控除率は70%~80%とされることが多くなっています。
しかしながら、独身男性における生活費控除率の主張立証と同様、高齢者の年金収入についても、生活状況を細かく伝えていくことで、生活費控除率50%以下での解決が可能となることがあります。
80代半ばの年金収入について生活費控除率30%で死亡逸失利益を認めさせた解決事例

 弁護士
弁護士
