後遺障害等級一般論 上肢 下肢 神経症状
rsd(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、crps(複合性局所疼痛症候群)のtype Ⅰ に分類される、rsd(反射性交換神経性ジストロフィー)について整理しています。
→crps(複合性局所疼痛症候群)一般についてはこちらの記事で整理しております。
rsd(反射性交換神経性ジストロフィー)とは
反射性交換神経性ジストロフィーは英語で reflex sympathetic dystrophy と表記しますが、rsdはその頭文字からなる略称です。
現在では大きくはcrpsの中に含まれ、crps type Ⅰ をrsd、crps type Ⅱ をカウザルギーと区別しています。前者は神経損傷が認められない場合、後者は神経損傷が認められる場合です。
rsdは反射性交換神経性ジストロフィーの略語ですが、rsd症状の原因が交感神経系の局所性過興奮であると説明されていた時期があったことがその由来です。しかし現在、多くの症例で交感神経の過活動が認められないことが確認されています(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、547頁)。
自賠責保険や労災保険が症状固定時の症状についてrsdだと認めれば、神経症状7級、9級、12級のいずれかでの認定可能性があります。
rsdの原因
骨折、靱帯損傷、打撲症、手術・注射、心筋梗塞、脳卒中などの疾患が原因になると言われます。
rsdの症状
疼痛(灼熱痛)、アロディニア(誘発痛)、浮腫(腫れ)、皮膚の変化(色、温度、形態など)、発汗異常、関節可動域制限、骨委縮など
灼熱痛
灼熱痛とは、肌が熱くてひりひりするような感覚。焼け付くような感じを言います。
アロディニア(誘発痛)
アロディニアとは、風があたっただけでも痛い、人の手が触れただけでも飛び上がるほど痛い、着ている服が擦れただけでもすごく痛い、というものです。
皮膚の変化
皮膚の萎縮(皮膚の乾燥化(カサカサする)、硬質化(カチカチになる)、光沢化(テカテカする)、鱗状化(ザラザラになる))、浮腫化(腫れ)、色変化(黒ずむ)、等。)、爪の異常変化、皮膚の温度変化など。
後遺障害等級の認定について
まずは、自賠責保険が示すrsdの要件をクリアする必要があります。
クリアすれば、あとはrsdとして何級なのか(7級、9級、12級のいずれか)、という問題になります。
「rsd」として審査されるための要件
交通事故等の外傷後に疼痛(灼熱痛)、アロディニア(誘発痛)、発汗異常、関節可動域制限などの症状が発生し残存してしまったとして、注意しなければいけないのは、医師がrsd(crps type Ⅰ)と診断する際の指針と、自賠責保険が後遺障害を「rsd」として扱う基準は別であり、後者の方がハードルが高いということです。
具体的にいうと、自賠責保険が症状固定時の症状をrsdとして審査するためには、次の3要件のすべてについて、患側と比較して明らかに認められる場合でなければいけません。これらの要件を満たさない場合、自賠責保険が残存症状についてrsdだという前提で審査することはありませんので、疼痛等の症状については神経症状12級~14級での認定が限界になってしまいます。
少し込み入った話になりますが、自賠責保険の認定結果が必ず真実だというわけではありませんので、自賠責保険がもしrsdとしての認定をしなかったとしても、裁判所へ訴訟提起して、後遺障害がrsdであると主張する(rsdなので7級だ!あるいは9級だ!など。)ことは可能ではあります。ただ、rsd含むcrpsの正確な発症メカニズムは不明だと言われていたり(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、547頁)、事故前から抱える心因性要素が影響すると言われることもある複雑な症例のため、裁判例の多くは自賠責保険での認定結果を重視する傾向にあります。まずは次の3要件を把握し、しっかり証拠の収集をしていく意識が重要だと考えます。
なお、逆からの発想ですが、これら3要件については、痛みのために患肢の運動を患者が随意に制限していることが原因になっていることも少なくないと考えれらるようになってきています(複合性局所疼痛症候群(CRPS)をもっと知ろう(全日本病院出版会)、13頁)。
1:関節拘縮
健側と比べて、rsd症状を呈している患部の関節に可動域制限(他動値)があるのかどうか。
2:骨の委縮
レントゲン画像で判断します。
レントゲン画像では通常、骨は白く映ります。骨萎縮がある場合、骨密度の低下によって、その白色が薄く透けて見え、健側の骨に比して黒く見える部位が多くなります。
3:皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の委縮)
皮膚の萎縮(皮膚の乾燥化(カサカサ化)、硬質化(カチカチ)、光沢化(テカテカ)、鱗状化(ザラザラ))、浮腫化(腫れ)、色変化(黒ずむ、等。)、爪の異常変化、皮膚の温度変化(高くなる場合も、低下する場合も両方ある。)が、健側との比較により認められるかどうか、です。
左右差がわかるカラー写真があれば、後遺障害申請時に提出することをお勧めします。
皮膚温変化は、サーモグラフィー検査で評価します。温度差が出ていれば、それも提出すべきです。
後遺障害等級の種類
上記3要件をいずれも満たした場合、あとはrsdとして何級になるのかという話になります。
自賠責保険としては、上記3要件に関連する所見の程度及び関節拘縮の程度等を参考にして、以下の3つのいずれかに認定するとしています。
| 別表第二第7級4号 | 軽易な労務以外の労働をするには差し支える程度の疼痛があるもの |
| 別表第二第9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
| 別表第二第12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
とはいえ、基準だけみても曖昧で、実際に残存した症状が何級として評価されるのが妥当なのか、判断に迷う場合が多いです。
弁護士法人小杉法律事務所の弁護士の感覚としては、神経症状と関節拘縮が生じている範囲がどの程度なのか(三大関節+指のすべてなのか、三大関節の1つだけなのか、手指だけなのか。例えば上肢なら、肩、肘、手首と手指すべてなのか、肘だけなのか、手指だけなのか、など。)(広いほど認定等級が重くなる可能性が高い。)、また、異常が生じている範囲について、特に骨委縮の範囲や程度(レントゲン画像で客観的に判断可能。)等の裏付けがあるのかどうかを考慮し、7、9、12級の峻別がなされている印象を持っています。
必要な検査や注意点など
関節拘縮
健側と比べて、rsd症状を呈している患部の関節に可動域制限(他動値)があるのかどうかです。
健側との比較になるということ、他動値での検査になるということ、ご留意ください。
※他動値:他人が動かしてどこまで動くのか。反対は自動値で、こちらは自分の意志でどこまで動かせるのか。
骨の委縮
レントゲン画像で判断します。こちらについても健側との比較が必要ですので、患側だけの撮影にならないようご留意ください。
皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の委縮)
こちらについても健側との比較が必要です。診察の際必ず医師に伝え、カルテに記載してもらいつつ、ご自身で写真撮影等なさって、証拠化しておくことをお勧めします。
その他
(複合性局所疼痛症候群(CRPS)をもっと知ろう(全日本病院出版会)、49頁、76~77頁)
発汗テスト、筋委縮の有無、発汗テスト等も有用です。
また、医療機関がCRPS(rsd含む)前提での治療をしていたかどうかという視点で、リリカ、ノリトレン、トリプタノール、ノイトロピン、オピロイド(麻薬性鎮痛薬。皮膚貼布薬もあり。)等の薬物処方の有無や程度、温冷交代浴や関節可動域訓練、電気刺激療法などの治療が行われたのかどうか、も考慮に入れる必要性があります。
交通事故等でrsd発症の際は弁護士に相談を
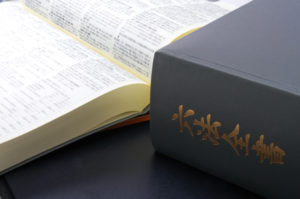
交通事故や労災事故等で受傷後にrsd症状が発生し残存した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷部位や態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。特に、骨折等の外傷を契機に発症した場合は当初は整形外科での治療になるかと思われますが、rsdは特殊かつ複雑な病態のため、かかっているお医者様が必ずしもrsdについて理解があり、適切な診断・治療をすることができるとは限らないという点です。そのような場合、例えばペインクリニックへのセカンドオピニオンや転院等も検討しなければいけませんが、そのような点も含め、ご不明点があれば相談時にお問い合わせください。
 弁護士
弁護士