弁護士の異議申し立てで後遺障害14級獲得&退職前給与で逸失利益認定
交通事故被害者Gさん 50代・男性・無職・福岡市南区
交通事故 後遺症・後遺障害

福岡県内の交通事故で怪我を負い、腰痛等の後遺症が残ったGさん。Gさんは腰痛で仕事を続けることができず、退職してしまうほどでした。
しかし、自賠責保険に後遺障害認定の申請をしたところ、非該当という判断が下されました。
納得できないGさんが弁護士に依頼した結果、異議申し立てで後遺障害等級14級を獲得&退職前年収で逸失利益が認定されました。
痛みについて認定される後遺障害等級14級は他覚的所見(症状の原因が客観的に分かる画像等)があるとは言えないが、痛みが残存すると自賠責保険が認定してくれる等級です。
客観的に症状の原因が分かる根拠が無いにもかかわらず、被害者の身体には本当に痛みが残存しているのだと認めてもらわなければいけないわけですから、
後遺障害等級非該当から後遺障害等級14級を認定してもらう異議申し立ては、弁護士の力量に最も大きく左右される業務の1つかもしれません。
このページでは、弁護士木村治枝が、いかにして異議申し立てにより後遺障害等級14級を獲得したのか?をメインに、
退職前年収での逸失利益の認定を含め、被害者Gさんの事例を解説していきます。
小杉法律事務所では、後遺症被害専門弁護士が無料相談を受け付けております。
自賠責の後遺障害等級の認定結果に納得がいかない等のお悩みをお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
交通事故・治療の状況

Gさんは仕事を終え、自動車で帰宅中でした。
福岡県太宰府市内の道路を走行中に、前の自動車が急停止したのでGさんも停止したところ、
後ろから脇見をしておりGさんが停止したことに気が付かなかった自動車が高速度で追突してきました。
車の天井が曲がる程の大きな衝撃でした。
幸い、骨折等の大怪我にはならなかったものの、頚椎捻挫・腰椎捻挫・胸部痛などの怪我をしました。
仕事の合間を縫い、週2~3日の通院治療を続けていく中で、頚部捻挫や胸部痛などに関しては完治したものの、
もともと腰痛を抱えていたことがあった腰椎捻挫に関しては治療を続けても良くならず、事故から6か月ほど経っても、被害者Gさんの身体には腰痛が残ってしまっていました。
しかし、仕事の都合からこれ以上の通院が難しくなったため、保険会社担当者に相談したところ、
後遺障害等級認定の申請をした方が良いと打診され、申請をします。
申請の結果は後遺障害には該当しないと判断するというものでした(=非該当認定)。
被害者Gさんは仕事を辞めざるを得ないほど腰痛に悩まされているにもかかわらず、
後遺障害非該当という判断が下されたことにどうしても納得がいかず、弁護士に依頼することを検討します。
そこで、後遺障害等級の認定が可能な弁護士を探し、小杉法律事務所にたどり着き、弁護士木村治枝の無料相談を受けることとなりました。
弁護士木村治枝の無料相談

弁護士木村治枝と被害者Gさんとの無料相談はお電話にて行いました。
当事務所ではご来所頂いての面談はもちろん、お電話や、Zoomでの相談も受け付けております。
被害者Gさんが気にしていたポイントは大きく分けて3つでした。
- 後遺障害等級の認定がされる可能性があるか。
- 利用できる弁護士費用特約がないため、費用倒れに終わる可能性があれば依頼できない。
- 依頼した後の流れと、想定される獲得額。
弁護士木村治枝は、被害者Gさんの疑問に1つずつ回答します。
1.後遺障害等級の認定がされる可能性がある?
弁護士木村治枝の回答:あります。
腰椎捻挫による腰痛について認定される可能性がある後遺障害等級は、第12級13号か第14級9号です。
- 第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第14級9号 局部に神経症状を残すもの
後遺障害等級第12級13号と第14級9号の分水嶺は「他覚的所見(症状の原因が客観的に分かる画像等)があるか」です。
したがって、第14級9号が該当する条件を充たし、他覚的所見があれば12級13号が認められるということになります。
第14級9号が認められるための条件は、以下のとおりです。(詳しくはむち打ち徹底解説のページをご覧ください。)
- 常時の痛みやしびれであること⇒〇
- 事故態様が軽微ではないこと⇒?
- 症状の推移に不自然さがないこと:事故直後が最もひどく、治療を続けていくに従い良くなっているか⇒〇
- 所見がないとはいえないこと:症状の原因となり得る変性所見が一切ないわけではないこと。⇒?
- 通院頻度や通院期間が適切であること:週2~3回 6か月⇒◎
- 通院先の病院の選定を間違っていないこと:整形外科通院が望ましい⇒〇
事故態様が軽微ではないこと について
上でも述べたように、被害者Gさんが乗車していた自動車は天井が曲がる程の大きな衝撃を受けていました。
ですので、この条件を十分に充たしているといえます。
ただし、自賠責に対する後遺障害等級認定の申請の際に通常提出する事故発生状況報告書は、
あくまで交通事故がどのようにして発生したか=被害者の過失がどれくらいかを認定するための一要素に過ぎず、
事故態様の大きさや交通事故により被害者が受けた衝撃を証明するためには不十分です。
弁護士木村治枝は整備会社に協力を仰ぎ、天井部分が曲がってしまった事故車の車両写真を取り付けて、
異議申し立ての際に提出することで交通事故態様の大きさを証明しますと伝えました。
所見がないとはいえないこと:症状の原因となり得る変性所見が一切ないわけではないこと について
被害者Gさんが治療のために通院していた病院では、レントゲンの撮影しか行っていませんでした。
頚椎捻挫や腰椎捻挫といった傷病から発生する痛みやしびれの原因は、椎間板が脊髄や神経根を圧迫するヘルニアであることが多いですが、
こういったヘルニアを示す画像は、レントゲンでは確認しづらく、MRI画像の方が映りやすいです。
したがって弁護士木村治枝は、被害者GさんにMRI撮影を依頼しました。MRI撮影画像でヘルニアの所見があれば、後遺障害等級12級13号の可能性も出てきます。
2.利用できる弁護士費用特約がないため、費用倒れに終わるなら依頼できないがその可能性はある?
弁護士木村治枝の回答:通院期間からすれば、万が一後遺障害等級が獲得できなくても弁護士入れた方が得。しかも利用できる弁護士費用特約がある。
交通事故によって生じた損害に対する賠償額を算定する基準は、大きく分けて3つです。
- 必要最低限の賠償を保障した、自賠責基準
- 自賠責基準と同額か、それよりはやや高いものの、適切な賠償額とまではいえない任意保険基準
- 裁判所が認定してくれる、最も適切な賠償額といえる裁判基準(弁護士基準)
任意保険基準は、自賠責基準よりは高くなくてはなりません。でなければ、任意保険に加入する意味がありません。
一方で、保険会社は営利企業ですから、できるだけお支払いする金額を低くしようとします。被害者にお支払いする金額が低くなればなるほど、それだけ保険会社の利益が上がります。
そこで、任意保険会社というのは、なるべく慰謝料額などの賠償金を自賠責基準と同額かそれに近くなるように算定してきます。
他方で、最も適切な損害賠償額は裁判所が認定してくれる裁判基準額です。弁護士が介入し、示談交渉が進まずに裁判になれば、
最終的には裁判所が最も適切な損害賠償額を認めることになります。
任意保険会社はできるだけ長期間に及ぶことになる裁判は避けたいですから、弁護士が介入した時点である程度慰謝料額などを上げざるを得ません。
これが、弁護士が介入するだけで慰謝料が上がるからくりです。
ですが、仮に弁護士が介入するだけで慰謝料額が上がったとしても、その上がった額より弁護士費用の方が高くなるのであれば依頼する意味はありません。
そこで、弁護士木村治枝は、被害者Gさんの通院期間から算出される任意保険基準の慰謝料額と、裁判基準の慰謝料額とを比較し、
弁護士費用特約が無くても弁護士に依頼した方が得をする旨を説明しました。
更に、被害者Gさんは弁護士費用特約を使えないと言っているが、利用できる弁護士費用特約があるかもしれないというお話をしました。
交通事故の事案ですと、その時乗車していた自動車等に付帯した保険の弁護士費用特約しか使えないと思われがちですが、
実際にはご家族が加入されている他の保険や、火災保険等にも、交通事故に利用できる弁護士費用特約が付いている場合があります。
被害者Gさんも交通事故時に乗車していた自動車に付帯した保険を見て、弁護士費用特約が使えないと思っていましたが、
確認したところ、会社が加入している保険で弁護士費用特約を利用できることが判明し、実質負担0で弁護士に依頼することができました。
3.依頼した後の解決までの流れは?
弁護士木村治枝の回答:まずは異議申し立てで後遺障害等級獲得を全力で目指す。獲得できれば示談交渉。できなければ裁判か紛争処理申請。※逐一被害者Gさんと相談して決定。
小杉法律事務所では、弁護士の独断で方針を決定することはありません。
依頼者の方と相談し、依頼者の方にとって最も良い結果になるようにしていきます。
被害者Gさんの事例でも、最初の無料相談時に考えられる事件解決までのルートを提示した上で、分岐点ごとにGさんに確認を取りながら進めて行きました。
費用倒れの心配もなく、今後の見通しもついたため、Gさんには安心してご依頼いただきました。
弁護士の介入①異議申し立てにより後遺障害等級14級を獲得!
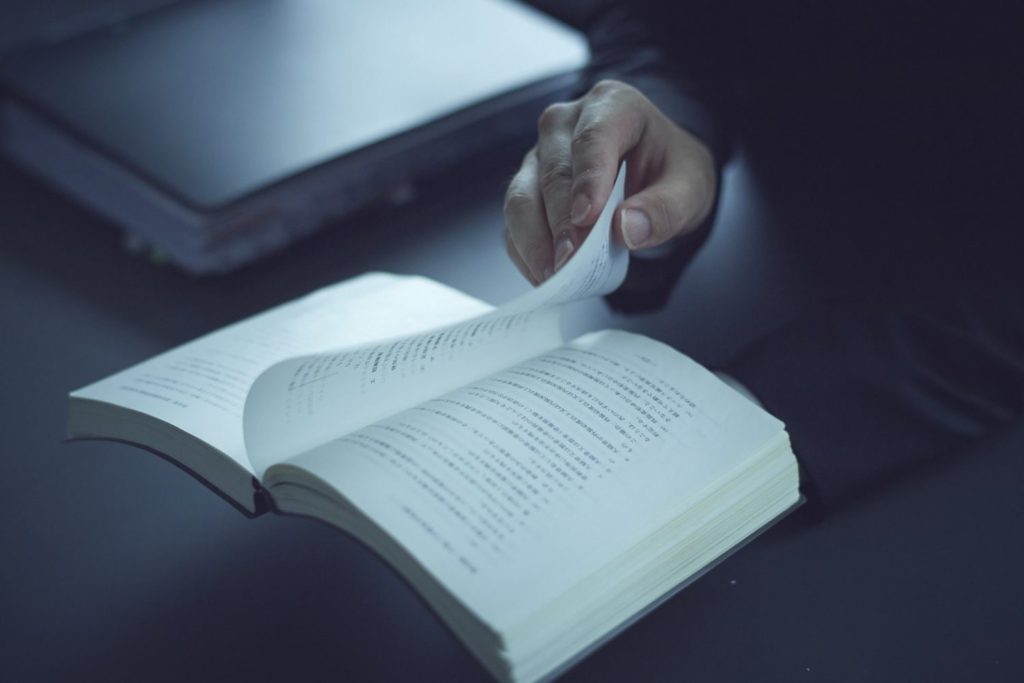
当たり前ですが、異議申し立てをしても、後遺障害等級非該当の認定を受けた際に提出した書類をそのまま出しただけで等級の変更はあり得ません。
また、「私は後遺症のせいでこんなに大変な状況になっているんです!」といった被害者の方の陳述書のみを提出しただけでも、後遺障害等級は変更にならないことがほとんどです。
異議申し立てによる等級認定の変更を目指すためには、新たな客観的な証拠を提出する必要があります。
この新たな客観的な証拠をどうやって集めるか、そして集めた証拠をどう使うかに弁護士の技量が表れるといってよいでしょう。
今回被害者Gさんの異議申し立てにおいて絶対に主張しなければならないのは、
- 事故態様が重大であること
- 所見がないとは言えないこと
の2つです。また、確実に等級の認定をしてもらうために、
- 症状の推移が不自然でないこと
についても主張を行うことにしました。
事故車両の写真や修理見積を提出し、交通事故態様が重大であることを主張
交通事故態様が重大であることを主張するために、事故車両の写真と修理見積を提出しました。
事故車両は天井が曲がる程の衝撃を受けていましたから、事故車両の写真は事故態様の重大さを示すことにもってこいです。
また、修理見積は、その名のとおり修理に必要な費用の見積もりです。修理に必要な費用の見積もりが高ければ、それだけ交通事故による破損の程度が酷い=事故態様が重大であるということができます。
そして、本件事故態様が加害者の脇見による追突であることも主張しました。
追突は、追突されて衝撃を受けるまで何も身構えることができません。また、真後ろから衝撃を受けるため、
不意に真後ろから衝撃を受けることで、首・腰の過屈曲・過伸展が起きやすくなり、怪我をしやすくなります。
そして、加害者は脇見運転をしており、ブレーキを踏んだりといった停止措置を何ら講じることなく、
減速せずにGさんの車両に追突しましたから、被害者Gさんが受けた衝撃は大きかったといえるでしょう。
MRI画像を提出し、所見がないとは言えないことを主張
弁護士木村治枝の依頼により、被害者GさんにMRI画像を撮影してもらったところ、Gさんの腰部にはヘルニアの所見が確認されました。
しかし、このヘルニアは事故のような外部からの衝撃により生じた外傷性のヘルニアではありませんでした。
おそらく被害者Gさんがもともと抱えていた腰痛の原因だと思われます。
この所見を用いて、「症状回復の阻害要因となるような異常所見(ヘルニア)があるのであるから、
異常所見が何ら無い者と比較すれば症状が残存しやすい」といった主張を行いました。
通院した病院のカルテを提出し、症状の推移が不自然でないことを主張
症状の推移を確認するには、通院した病院のカルテ(診療録)を見るのが一番です。
被害者Gさんが通院した整形外科のカルテをすべて読み、その中で「腰部痛」について触れている箇所を時系列順にまとめて提出しました。
「腰部痛あり」「腰部痛持続」「特に変わりなし」といったカルテ上の記載は、治療を続けていっても変わらず被害者Gさんの腰痛が残存していることを証明する証拠になります。
医師が治療を良く行ってくれているので、正直にあまり症状が変わらないと伝えるのは申し訳ないと思い、
「良くなっている気がします」というようなことを医師に伝えてしまったりする方がいらっしゃいます。
ですが、こういったコメントはカルテに残ってしまい、「良くなったり悪くなったりしているのは症状の推移として不自然」といった認識を自賠責にされかねません。
もちろん嘘はいけませんが、医師に自覚症状を伝える際には正直に伝えましょう。
新たに入手した証拠に基づく主張が功を奏し、異議申し立てにより後遺障害等級14級が認定されました。
弁護士の介入②示談交渉により退職前の年収を基礎収入認定!
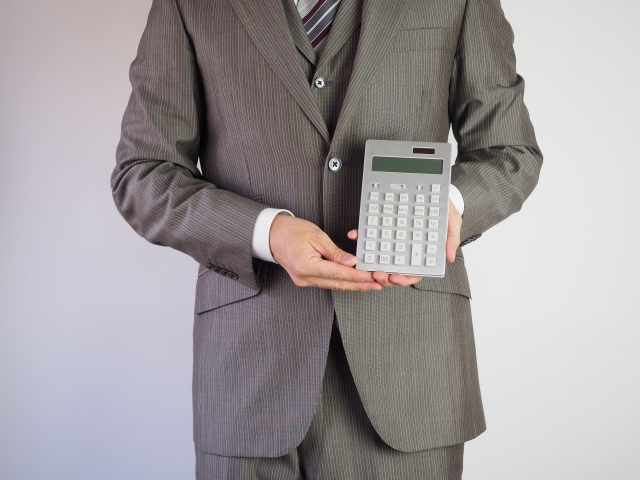
後遺障害等級が狙いどおり認定されたので、被害者Gさんと相談し、示談交渉に進むことになりました。
基本的に、後遺障害等級が認定される事例での損害賠償金の多くを占めるのは逸失利益です。
逸失利益算出の基本的な考え方は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間となっています
(実際には中間利息控除を考慮し労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じます。)。
この人は今後〇円の収入(基礎収入)を得る能力があるが、残存した後遺障害によりその△%が喪失した(労働能力喪失率)。
その後遺障害により労働能力を△%喪失した期間が今後☆年続くだろうから、〇円×△%(後遺障害が残存したことにより稼ぐことができなくなった年額)×☆年で、
将来にわたって後遺障害が残存したことにより逸失した利益を算出できる、というわけです。
つまり基礎収入は「この人は今後〇円の収入を得る能力がある」と証明できた額になります。
しかし、被害者Gさんは交通事故以前に従事していた仕事を退職していました。言い換えれば労働能力喪失率は100%です。
もちろん交通事故により腰痛を抱えてしまったことが退職の直接の原因ではありますが、自賠責に認定された後遺障害等級はあくまで14級です。
自賠責基準でも裁判基準でも、後遺障害等級14級の労働能力喪失率は5%とされています。
個別具体的な事情により後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率以上の喪失率が認定される場合はありますが、
後遺障害等級14級で100%の労働能力喪失率が認められることはまずあり得ません。
仮に後遺障害等級14級が認定されるような後遺症が残存したために退職した人に100%の労働能力喪失率が簡単に認められるのであれば、
今後得ることになる収入全額を簡単に加害者側に払ってもらえるという話になってしまいます。
ですので、現実的には後遺障害等級14級が認定されるような後遺症が残存し、それにより失業したと主張してもまず認められません。
では、被害者Gさんと同じような事案で、逸失利益は一切認められないのか?最悪の場合はあり得ます。
ですが、被害者Gさんの事例では弁護士の主張により事故前の収入を基礎収入として逸失利益が認定されました。
その理屈はこうです。
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』では、失業者の後遺症逸失利益の基礎収入は次のように決定されるとされています。
「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある者は認められる。再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、その場合特段の事情のない限り失業前の収入を参考とする。」
被害者Gさんは後遺症の影響で失業していましたが、失業給付を受けつつ経理の勉強をするために学校に通っていました。
弁護士はこの事実を証拠とし、被害者Gさんは労働能力も労働意欲もあり、就労の蓋然性があると主張したのです。
特段の事情のない限り失業前の収入を参考とするとされていますから、交通事故前に勤めていた会社での収入を基礎とし、逸失利益を主張、その全額が認定されました。
逸失利益は全額、入通院慰謝料や後遺症慰謝料については裁判基準のほぼ満額が認められました。
当然ですが、後遺障害が認定されない場合には逸失利益や後遺症慰謝料は0円です。
弁護士の介入により、Gさんは自賠責保険金を含め約280万円の増額を受けることになりました。
逸失利益についてのより詳しい解説はこちらのページからご覧ください。
依頼者の声(福岡市南区在住・男性・50代)

私の身体には間違いなく後遺症が残っているのに、それが認定されないということにどうしても納得できませんでした。
結果的に後遺障害が認定されたのは木村弁護士のお力添えのお陰です。
また何かあった際にはまず木村弁護士にご連絡したいと思えるほど納得いく解決をして頂きました。
弁護士木村治枝のコメント:異議申し立ては弁護士の手腕が問われます。

異議申立てはいかに新しい証拠を集められるか、いかにそれをもとに説得的な主張ができるかによって等級が上がる可能性が大きく変わります。
小杉法律事務所では後遺症被害専門弁護士が、適切な証拠を集め、的確な分析をし、説得的な主張で異議申し立てで等級が上がる可能性を大きく押し上げます。
ご自身の認定された等級に納得がいかない方は、ぜひ一度、お気軽に後遺症被害専門弁護士の無料相談をお受け下さい。

 弁護士
弁護士
