脳損傷 神経症状
【高次脳機能障害は弁護士に相談を】慰謝料請求/後遺障害等級認定専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、高次脳機能障害の事案で弁護士に相談・依頼した方がよい理由について整理しています。
なお、本記事の医学的事項については医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)が記事監修を行っています。
高次脳機能障害とは
高次脳機能とは、人間が社会生活を営む中で学習し身につける、「言語」、「空間や対象の認知」、「記憶」、「計画的行動」、「論理的思考」等を意味するとされています。
そして、高次脳機能障害は、病気や頭部外傷などの原因により脳に損傷をきたしたために生じる、言語能力や記憶能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障害を指します。日常生活における具体的症例としては、今朝の朝食の内容を思い出せない(記憶障害)、仕事や作業に集中することができない(注意障害)、計画が立てられなくなる(遂行機能障害)、言葉を上手く話すことができなくなったり人の話が理解できなくなった(失語症)、お箸や歯ブラシの使い方が分からなくなった(失行症)、左側になるおかずが目にとまらず残すようになった(左半側空間無視)などが挙げられます(参考:「高次脳機能障害者地域支援ハンドブック」(改訂第五版))。
高次脳機能障害は交通事故等の頭部外傷で生じることがありますが、必ずしも外傷性のものとは限りません。
たとえば、通常頭部外傷とは無関係の脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)、脳腫瘍、脳感染症など、脳に損傷や機能異常をきたすものであればいずれも原因になります。
高齢者の場合、既往症に何らかの高次脳機能障害を示す疾患があり、その後に頭部外傷を負うことや、その逆も考えられ、外傷の影響がどこまでなのか悩ましいケースもあります。
厚生労働省が示す高次脳機能障害の診断基準によれば、高次脳機能障害は以下2点を主要症状とするものであるとされています。
①脳の器質的病変の原因となる疾病の発症や事故による受傷の事実が確認されている
②現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である
これより、高次脳機能障害の診断にあたっては、脳自体(物理的意味での)に何らかの異常があることが必要とされているものといえます。
もっとも、この基準の表現は曖昧なところがあり、また病変原因も複数を含むものであることから、
交通事故等の外傷によって高次脳機能障害が発症したといった場合に、前記のような争いが生じることが多いといえます
→高次脳機能障害の症状についてはこちらの記事で詳細を整理しています。
認定されうる後遺障害等級の区分
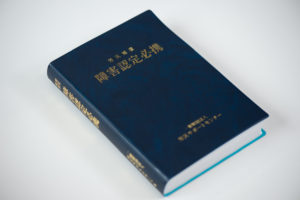
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。
| 別表第一第1級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」をいい、「身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの」もこれにあたります。 |
| 別表第一第2級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」をいい、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」がこれにあてはまります。 |
| 別表第二第3級3号 | 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」をいい、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第5級2号 | 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」をいい、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第7級4号 | 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」をいい、「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第9級10号 | 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」がこれに該当します。 |
後遺障害等級認定のポイント
自賠責保険が脳外傷による高次脳機能障害を認定する際のポイントは次の3つです。
これらを総合考慮して、脳外傷による高次脳機能障害として認定できるか否か、認定できるとして程度は(何級なのか)が判断されます。
最も重視されているのは1の画像所見の有無です。
1:交通外傷による脳の損傷を裏付ける画像検査結果があること
2:一定程度の意識障害が継続したこと
3:一定の異常な傾向が生じていること
→高次脳機能障害についての後遺障害認定のポイントについては「高次脳機能障害の等級認定と金額について」の記事で詳細を整理しています。
頭部外傷後、早期に弁護士に相談すべき理由

高次脳機能障害が分かりにくい障害だからこそ
交通事故等の頭部外傷で高次脳機能障害を発症した被害者の方自身では、自分にどのような症状が発生しているのか把握することが困難なケースが多いです。また、他者に気付かれにくい高次脳機能障害について、ごく限られた時間内でなされる主治医との診察のみでは、主治医も高次脳機能障害に気づきにくい面があります。
ですので、まずは被害者に身近な人物で事故前後を通じて被害者の状況に変化があったかどうかを確認できそうな人物を探すのが大事です。
同居の家族がいれば適任ですが、記憶障害(思い出せない、覚えられない)、注意障害(集中できない、持続力が無い)、遂行機能障害(段取りが悪い、臨機応変に動けない)、社会的行動障害(すぐ怒る、意欲が無い、物事に固執する)等がありそうだということでしたら、症状固定前の段階でもひとまず「日常生活状況報告」記載の事項について聴取し(その時点での確認用・参考用として書式そのものを作っていただくのもいいかもしれません。)、高次脳機能障害が疑われたら主治医との相談を勧め、高次脳機能障害になっていないか、疑わしいなら必要な検査や治療がなされているのかなどを確認してみるのがよいでしょう。
弁護士法人小杉法律事務所の弁護士が法律相談時に「頭部外傷による高次脳機能障害かも?」と感じた場合、ご本人様の相談なら「事故後に性格が変わった、と言われないか?」「以前は問題なくできていた作業が難しくなったりしてないか?」など聴取し、場合によってはご本人様の許可を取ったうえで同居の親族等に連絡させていただいて同様のことを聴取する等することで、懸念はないのか確認するように努めております。
その中で、弁護士目線で高次脳機能障害が疑わしい状況である場合には、主治医に相談することをお勧めしたり(ご本人様での対応が難しい場合、親族同伴で診察に行ってもらい、状況を説明してもらうようお勧めすることもあります。)、ご依頼後であればこちらから主治医にコンタクトをとって直接確認する等の対応も可能です。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定に必要な検査の実施、書式の取付け
高次脳機能障害が発生していること、それが頭部外傷に起因すること等を立証するために、必要になる検査や取りつけるべき資料・書式は多いです。
そのため、漏れがないように資料を収集し、内容について必要な記載がなされているのか確認することが非常に重要になるといえます。
特に画像検査については、びまん性脳損傷の場合は急性期の脳CT画像上はっきりした異常所見が確認できないため、後遺障害・賠償上の観点からすればMRI撮影や経時的な脳画像の撮影がなされることが望ましいところではありますが、他方、医療機関の目的は治療であり、少しでも症状を治すことを目指して医療行為が行われていることから、時には後遺障害等級認定上では重要となるような検査がなされないこともあるかもしれません。
ここで、後遺障害等級認定に精通している弁護士等の専門家が関与することによって、医療機関や医師に、後遺障害等級認定に向けての具体的な協力を仰ぐことができるようになります。法律相談時に弁護士からアドバイスさせていただいたり、ご依頼後であれば弁護士から医師に直接コンタクトを取っていくことも可能になります。
高次脳機能障害被害者ご本人やご家族の気持ちを汲んだ損害賠償請求内容になっているか
高次脳機能障害の場合、重度の場合は将来介護費や将来治療費、家屋の改造費用や福祉車両に関連する請求項目についてもれなく検討しなければいけません。
他方、被害者本人に発生する慰謝料は当然のこととして、典型的には同居して日々被害者の方と接して介護に携わらなけれないけないご家族の固有の慰謝料を請求する必要があります。
→高次脳機能障害で注意すべき損害賠償費目については「高次脳機能障害の等級認定と金額について」の記事で詳細を整理しています。
高次脳機能障害に関することなら弁護士法人小杉法律事務所の弁護士に相談を

交通事故等で頭部外傷を負い外傷性の高次脳機能障害を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所では高次脳機能障害被害に関する無料相談を実施しておりますので、所属弁護士に是非ご相談ください。
高次脳機能障害に関連する弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

→【高次脳機能障害】医師の意見書により交通事故との因果関係を繋げ自賠責併合4級の判断を裁判で1級に変更
→【高次脳機能障害】①約2200万円の示談提示⇒約8300万円で解決。②介護状況を具体的に立証し、自賠責3級認定を裁判で2級獲得
→【高次脳機能障害】医師の意見書が決め手となり、賠償金約2.5億円獲得
 弁護士
弁護士