Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/1/kosugi-lawyer/web/personal-injury/fatal-accident/wp-content/themes/php/single.php on line 32
死亡事故刑事裁判への被害者遺族の参加(弁護士小杉の講演内容抜粋)
2023.12.26

弁護士法人小杉法律事務所の代表弁護士小杉晴洋が【死亡事故刑事裁判への被害者遺族の参加】について、弁護士向けに講演を行いました。
このページでは、刑事手続への被害者遺族の参加に関する法令解説部分のみを抜粋して紹介します。
死亡事故のご遺族に、法令上認められる権限などについて整理しております。
なお、弁護士法人小杉法律事務所における刑事裁判参加サポートについてはこちらのページをご覧ください。
- 死亡事故刑事裁判への被害者遺族の参加に関する刑事訴訟法の規定
- 刑事訴訟法第47条(刑事裁判開始前の訴訟に関する書類の公開について)
- 刑事訴訟法第290条の2(死亡事故において心情意見や被害者参加をすることのできるご遺族の範囲はどこまでか)
- 刑事訴訟法第292条の2(死亡事故のご遺族が刑事裁判において述べる心情意見陳述について)
- 刑事訴訟法第316条の33(死亡事故のご遺族が刑事裁判に被害者参加するには)
- 刑事訴訟法第316条の34(死亡事故のご遺族が刑事裁判に参加する場合の期日への出席について)
- 刑事訴訟法第316条の35(死亡事故のご遺族やその委託を受けた弁護士の検察官に対する意見について)
- 刑事訴訟法第316条の36(死亡事故のご遺族又はその委託を受けた弁護士が刑事裁判で証人尋問をすることについて)
- 刑事訴訟法第316条の37(死亡事故のご遺族又はその委託を受けた弁護士が刑事裁判で被告人質問をすることについて)
- 刑事訴訟法第316条の38(死亡事故のご遺族又はその委託を受けた弁護士による論告意見について)
- 刑事訴訟法第316条の39(死亡事故のご遺族が刑事裁判に参加する際の保護について)
- 死亡事故(交通事故)刑事手続への被害者遺族の参加に関する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
- 死亡事故(交通事故)刑事手続への被害者遺族の参加に関する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
- 死亡事故(交通事故)刑事手続への被害者遺族の参加に関する犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
- 死亡事故刑事裁判についての弁護士小杉晴洋のコメント
死亡事故刑事裁判への被害者遺族の参加に関する刑事訴訟法の規定
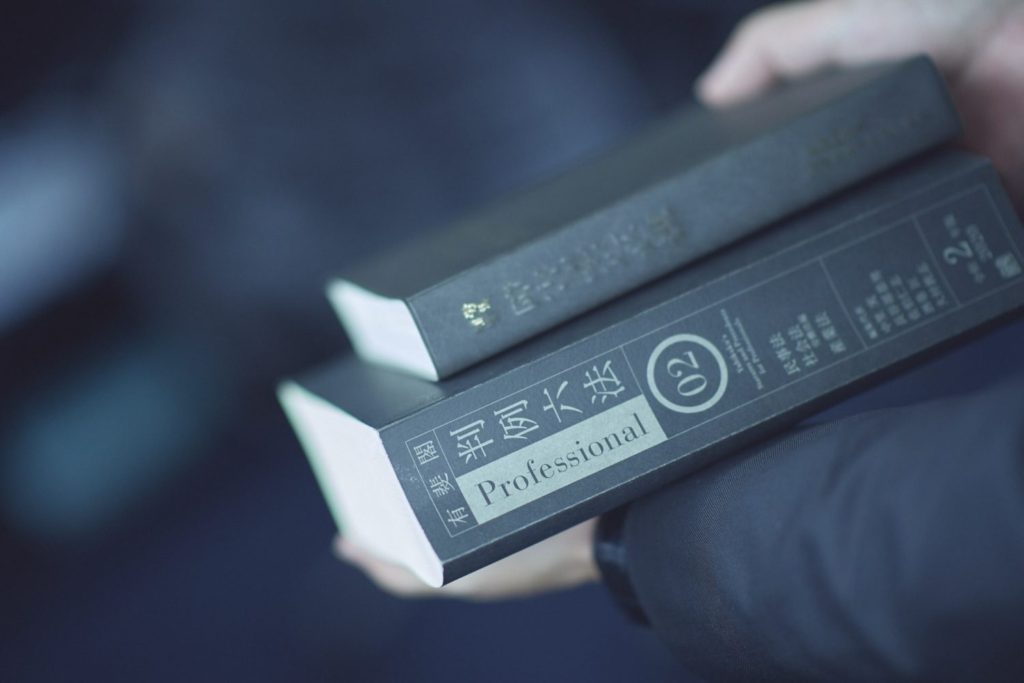
刑事訴訟法第47条(刑事裁判開始前の訴訟に関する書類の公開について)
(条文)
「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の理由があって、相当と認められる場合は、この限りではない。」
point:死亡事故遺族は刑事裁判が始まる前に刑事裁判に関する記録を閲覧謄写することができます
刑事訴訟法第47条では、原則として刑事裁判に関する書類は、刑事裁判が開始する前に公にされることを禁止していて、ただし、公益上の必要その他の理由があって相当と認められるときには、例外的に開示されるものと規定されています。
刑事裁判に関する書類を事前に見ることができないとなると、死亡事故遺族が刑事裁判において証人尋問・被告人質問・意見陳述等を行う上で支障がでますので、実務の運用としては、刑事訴訟上47条ただし書を根拠として、刑事裁判が始まる前に、起訴状、証拠等関係カード、検察官が裁判所へ提出する証拠などの閲覧やコピーができるようになっています。
捜査担当の検事と仲良くなっておくと、閲覧や謄写がスムーズとなりますので、捜査段階における死亡事故遺族側の弁護士の動きも重要です。
捜査担当警察官や検察官と仲良くなっておきスムーズに死亡事故刑事裁判に参加した解決事例はこちら
実際の運用のルールは検察庁によって異なりますが、複写の禁止や刑事裁判以外での利用禁止などの制限がなされることが多いです。
従いまして、検察官から入手した資料を民事での損害賠償請求の際に用いることはできませんので、注意が必要です(刑事裁判確定後に再度謄写申請をしなければなりません。)。
刑事訴訟法第290条の2(死亡事故において心情意見や被害者参加をすることのできるご遺族の範囲はどこまでか)
第1項(条文)
「裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。(以下略)」
point1:死亡事故において刑事裁判に参加できる遺族の範囲は、①配偶者、②父母・祖父母などの直系の親族、③兄弟姉妹と規定されています
刑事訴訟法第290条の2は刑事裁判への被害者参加に関する直接的な規定ではありませんが、この規定で、刑事裁判へ被害者参加できる遺族の範囲が定められています。
具体的には、被害者が死亡してしまった場合、被害者の①配偶者(妻又は夫)、②父母・祖父母などの直系の親族、③兄弟姉妹は刑事裁判に参加する資格があるとされています。
配偶者(妻)が死亡事故被害者の夫のために心情意見や被害者参加をした解決事例はこちら
ご両親が死亡事故被害者の子のために心情意見や被害者参加をした解決事例はこちら
祖父が死亡事故被害者の孫のために心情意見や被害者参加をした解決事例はこちら
妹が死亡事故被害者の兄のために心情意見や被害者参加をした解決事例はこちら
兄が死亡事故被害者の弟のために心情意見や被害者参加をした解決事例はこちら
point2:内縁の妻や内縁の夫は刑事裁判に被害者参加できません
この条文でいう「配偶者」には、内縁の夫や妻は含まないと解釈されていますので、内縁の配偶者を死亡事故によって亡くされてしまった事例では、刑事裁判に被害者参加することができません。
ただし、捜査担当警察官や検察官に事情を説明することにより、内縁の配偶者の「供述調書」を作成してもらうことはでき、これにより内縁の配偶者の意見を刑事裁判に証拠として届けることはできます。
同棲していた彼女の陳述書を提出して死亡事故事件の解決をした事例はこちら
刑事訴訟法第292条の2(死亡事故のご遺族が刑事裁判において述べる心情意見陳述について)
第1項(条文)
「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」
point:死亡事故の刑事裁判に参加する遺族は遺族の心情を刑事裁判において陳述することができます
心情意見陳述と呼ばれるものです。これは、被害者がお亡くなりになられてしまったことについての遺族の心情を伝えるものですから、被害者参加代理人の弁護士ではなく、遺族ご自身がされることを推奨しています。
ただし、どうしても直接法廷で話をするのが難しいというご遺族もいらっしゃいますので、そのような場合には、被害者参加代理人の弁護士が行うことになると思われます。
その場合も、心情意見陳述の原稿内容は、ご遺族とともに作成することになります。すべて弁護士が考えた作文では意味がありません。
なお、刑事裁判の心情意見陳述では、民事の損害賠償請求を見据えて、逸失利益の基礎収入額や生活費控除率など基礎情報を盛り込んだ方が良いという事例もございます。
第2項(条文)
「前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。」
point:死亡事故の刑事裁判で遺族の心情意見を行う場合は、あらかじめ検察官に申し出をしなければなりません
刑事裁判の手続として、心情意見を行う場合には、あらかじめ検察官に申し出をしておかなければなりません。
これは申出の書面を1通送るだけの手続的な条項となります。
また、被害者参加弁護士と遺族との間で協議を終え、心情意見陳述内容が完成したという場合は、その原稿を公判担当検察官にあらかじめ送付しておくことが多いです。
第3項(条文)
「裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。」
point:心情意見陳述を行ったご遺族に対して裁判官から質問がなされることはほとんどありません
私の経験上、心情意見陳述を行ったご遺族に対して裁判官から質問がなされたことは1度もありません。
ただし、どのような心情意見を陳述するのかについて、あらかじめ検察官及び裁判官に対して書面を提出するよう要求されることが多く、その際に、表現についての訂正を促されることがあります。
具体的には、①死亡事故というのは故意犯ではなく殺人罪には該当しないので「殺された」という表現は訂正できませんか?、②死刑にしたいと書いてありますが死亡事故の場合法定刑で死刑がないので表現を訂正できませんか?といった話がなされます。
これらの話は心情意見を行う刑事裁判の期日の前に行われますので、刑事裁判の当日に裁判官から訂正を促されたり質問がなされることはありません。
第4項(条文)
「訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。」
point:心情意見陳述を行ったご遺族に対して訴訟関係人から質問がなされることはほとんどありません
私の経験上、心情意見陳述を行ったご遺族に対して訴訟関係人から質問がなされたことは1度もありません。
なお、裁判官や検察官には心情意見陳述書の事前提出を行いますが、被告人ないし弁護人に対しては行いません。
第5項(条文)
「裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。」
point:心情意見陳述を行ったご遺族に対して裁判官から制限がなされることはほとんどありません
私の経験上、心情意見陳述を行ったご遺族に対して裁判長から制限がなされたことは1度もありません。
事前に心情意見陳述書を提出しているからというのもありますが、中には、心情意見陳述書に記載がないことを話し出すご遺族の方もいらっしゃり、しかも、予定時間をオーバーして意見陳述をされる方もいらっしゃいます。
故人に対する想いが溢れてしまったり、被告人への感情が強くなってしまうことは無理からぬところがありますので、これ自体は陳述者を責めるような話ではないのですが、このような事例であっても裁判官から制限がなされたということは一度もありません。
死亡事故の場合、人が亡くなっていますから、裁判所もその遺族への配慮というものをある程度考えているのだと思われます。
第6項(条文)
「第157条の4(証人への付添い)、第157条の5(証人尋問の際の証人の遮蔽)並びに第157条の6第1項及び第2項(ビデオリンク方式による証人尋問)の規定は、第1項の規定による意見の陳述について準用する。」
point:刑事裁判で意見陳述を行う際は、必ずしも法廷に一人で立って行う必要はなく、遺族を保護する制度が定められています
裁判官・検察官・被告人・弁護人・傍聴人が見ている中、刑事裁判の法廷で証言台の前に一人で立ち、意見陳述を述べるというのは、かなりの精神力を要します。
被害者参加代理人の弁護士が代わりに行うこともできますが、心情意見陳述というのは、できればご遺族の生の声で伝えた方が良い性質のものです。
そこで、刑事裁判の法廷で証言台の前に一人で立って話すことは精神的に難しいが、意見陳述自体は行いたいという事例では、意見陳述を行うことをやめるのではなく、付添い、遮蔽、ビデオリンクを利用して意見陳述を行う方が良いと考えます。
私の経験例では、夫を亡くした妻が、悲しみのあまり一人で立って歩くことも困難な状態となってしまったため、義姉を付添人として証言台の前に2人で立ってもらい、意見陳述をしてもらったという事例があります。
また、被告人を前にしては話せないというケースの場合は、被告人の前に遮蔽措置(パーテーションのようなもので壁を作って被告人から遺族を見えないようにします。)をとって意見陳述を行うということや、ビデオリンク方式で意見陳述を行うことも考えられます。
第7項(条文)
「裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。」
point:調書に残す便宜上この規定が使われることが多いです
刑事裁判で遺族が話した心情意見陳述内容を一言一句調書に残すのは、裁判所の事務処理上大変ですので、この条文を使って心情意見陳述書を提出させるという運用がなされることが多いです。
ただし、刑事裁判の法廷の場において遺族が生の声で心情意見を陳述することが禁止されるわけではなく、生の声でも心情意見の陳述はするが、心情意見陳述の書面も提出するという運用で行われています。
第8項(条文)
「前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。」
point:刑事裁判実務の運用では裁判長が意見陳述の書面を朗読したり要旨を告知することはなく、遺族又はその代理人が法廷で話をすることがほとんどです
刑事裁判実務の運用では、調書上は裁判長が朗読したように記載されることもありますが、実際は遺族又はその代理人が法廷の場で意見陳述を述べることがほとんどです。
第9項(条文)
「第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」
point:ご遺族の心情意見陳述は被告人の量刑判断のための証拠となります
この条文では、心情意見陳述は犯罪事実の認定のための証拠とすることができないと規定されていて、これは被告人が有罪か無罪かの判断の際の証拠としては使えないということです。
例えば、ひき逃げ死亡事故において、被告人が「自分は犯人ではない」と無罪を主張していた事例で考えると、裁判所は「遺族の発言からすると被告人が犯人である」であるとか「遺族の発言をもってしても被告人が犯人であるとはいえない」といった判断できません。
遺族の心情意見陳述は、被告人を懲役何年とするかといった量刑判断の際に証拠として用いることになっていて、遺族が心情意見陳述を行うと検察官の求刑どおり判決が出されるなど重い量刑判断がされることが多いです。
なお、遺族の発言を被告人の犯罪事実の認定のための証拠として使いたいという事例では、警察官や検察官に遺族の供述調書を取ってもらい、これを証拠として提出することが方法として考えられます。
刑事訴訟法第316条の33(死亡事故のご遺族が刑事裁判に被害者参加するには)
第1項(条文)
「裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。」
1号「故意の犯罪行為により人を死傷させた罪」
2号及び3号 略
4号「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第4条(過失運転致死傷アルコール等発覚免脱)、第5条(過失運転致死傷)又は第6条第3項若しくは第4項(無免許による加重)の罪(平成25法86本号追加)」
point:死亡事故の場合は、遺族の刑事裁判参加が許可されないということはほとんどありません
私の経験上、死亡事故の刑事裁判において、遺族の被害者参加が許可されなかったという事例は1度もありません。
第2項(条文)
「前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。」
point:検察庁によって書式が異なることがありますので、申出の前に検察庁に確認することをおすすめします
被害者参加の申出は検察庁によって書式が異なることがありますので、申し出前に管轄の検察庁に確認しておくことをおすすめします。
被害者参加手続の利用はあまり普及していませんので、本庁以外の検察庁ですと、手続にまごつくことがあります。
そうこうしている間に、裁判所―公判担当検察官-弁護人間で期日が調整されてしまっているといったこともありますので、注意が必要です。
被害者参加が想定される事例では、捜査段階からケアしておきましょう。
第3項(条文)
「裁判所は、第1項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなったことが明らかになったとき、又は第312条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときは、決定で、同項の決定を取り消さなければらならい。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至ったときも、同様とする。」
point:ほとんど使うことのない条文です
想定されるような事例はほとんどなく、気にしなくてもよい条文です。
刑事訴訟法第316条の34(死亡事故のご遺族が刑事裁判に参加する場合の期日への出席について)
第1項(条文)
「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。」
point:刑事裁判に被害者参加する場合は傍聴席ではなく法廷のバーの中へ入ることができます
刑事裁判に被害者参加をする場合は、傍聴席ではなく、法廷のバーの中へ入ることができます。
公判担当検察官の横の座席となることが多く、被害者参加弁護士と共に出廷する場合は、検察官・被害者参加弁護士・遺族と横並びでの着席となることが多いです。
また、広い法廷で刑事裁判期日が開かれる場合には、公判担当検察官の後ろの座席に着席となることもあります。
第2項(条文)
「公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。」
point:遺族の参加可能な日時で裁判期日は調整されます
条文上は、裁判所が定めた公判期日を遺族に通知するという規定になっていますが、出席できない期日を通知されてもしょうがありません。
実務上は、被害者参加する事例においては、遺族や被害者参加弁護士の予定も加味したうえで裁判期日が決定されます。
第3項(条文)
「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数ある場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。」
point:この条文が問題となることはほとんどありません
被害者参加人や被害者参加弁護士の人数が多すぎるときは、裁判所が代表者を選定して出席する人数を絞ることがあるという条文ですが、想定される事例はほとんどありません。
第4項(条文)
「裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。」
point:ほとんど使うことのない条文です
想定されるような事例はほとんどなく、気にしなくてもよい条文です。
第5項(条文)
「前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。」
point:気にしなくてもよい条文です
気にしなくてもよい条文です。
刑事訴訟法第316条の35(死亡事故のご遺族やその委託を受けた弁護士の検察官に対する意見について)
(条文)
「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し、又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。」
point:検察官の権限行使に関し意見を述べることができます
被告人の訴追は検察官の専権事項となっていますが、遺族や被害者参加弁護士は、検察官の権限行使に意見を述べることができます。
そして、検察官は、意見どおりの権限行使を行うか/行わないかの選択をすることになり、必要に応じて当該選択をとった理由を説明しなければならないとされています。
遺族の強い希望がある事例などではこの条文を使用することがありますが、検察官も被告人に刑罰を求めるという仲間のポジションにいますので、基本的には検察官の権限行使にケチをつけるという戦略よりも、戦略決定前に密なコミュニケーションを取りながら、「一緒に戦う」という姿勢で刑事裁判に臨むことをおすすめします。
私の経験上も、検察官に厄介がられるよりも、仲良くなった方が、刑事裁判の進行が上手く進むことが多いように思います。
検察官に遺族側の味方になってもらい、遺族側の要望を検察官自身が満たしたいと思ってもらえるような関係を築けることが理想と言えます。
刑事訴訟法第316条の36(死亡事故のご遺族又はその委託を受けた弁護士が刑事裁判で証人尋問をすることについて)
第1項(条文)
「裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出あるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。」
point:刑事裁判に被害者参加すると証人に対して尋問をすることができます
刑事裁判にご遺族が参加する大きな意義の一つとして、直接証人尋問を行うことができます。
ただし、情状に関する事項に限られますので、目撃者証人に対する尋問や、鑑定人証人・警察官証人などに対する尋問を行うことはできません。
死亡事故の場合、被告人の家族や上司が、情状証人として出てくることがありますが、その被告人の家族や上司に対して尋問を行うことができます。
ただ、尋問というのは、法廷で述べられた証言内容を証拠として使う(若しくは信用性がないとして使わせない)ためのものであって、テレビドラマのように、法廷の場で論破したり、追及したりするようなものではありません。
テレビドラマのような尋問をしようと思うと、裁判官の心証が悪くなってしまうこともあります。
そこで、ご遺族の方が強く望まれる場合は別として、そうでないのであれば、被害者参加代理人の弁護士がご遺族に代わって尋問をするのが望ましいと考えています。
なお、証人尋問の前には、公判担当検察官との打合せが行われることが多いです。
中にはご自由にどうぞと言って遺族側主導で尋問をさせてくれる検事もいますが、基本は事前に打合せを行います。
遺族側と検察官側とで、尋問で聞きたい事項を出し合って、どちらが何を尋問するかについて役割分担をします。
遺族の意向を聴いた上ですべての尋問を自分で行おうとする検察官もいますが、検察官に丸投げするのはおすすめしません。
被害者参加代理人の弁護士は、刑事事件は当然ですが、その後の民事事件の損害賠償請求も視野に入れていますので、被害者参加代理人の弁護士が尋問を行うのが望ましいと考えます。
死亡事故加害者サイドの証人に対して弁護士小杉が行った証人尋問の例はこちら
第2項(条文)
「前項の申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。」
point:実際は証人尋問期日の前に検察官に対して申出を行っています
この条文では、検察官の尋問が終わった後に、被害者参加人から証人尋問をすることの申し出を行うと規定されていますが、実務の運用では、証人尋問の期日の前に、証人尋問をするかどうかの打合せを検察官との間で行っていて、申し出を済ませています。
第3項(条文)
「裁判長は、第295条1項から第4項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。」
point:情状に関する事項以外についての尋問をしてしまうと裁判長から制限されてしまいます
例えば、情状証人である被告人の母親に対して、「本当に今後の監督を誓っているんですか?具体的にはどう監督するんですか?」などと尋問することは、情状に関する事項ですので制限されることはありません。
他方で、被告人がひき逃げ犯ではないと争っているような事例において「あなたのお子さんは●月●日●時頃、どこにいましたか?」などとアリバイに関する質問をすることは、犯罪事実の成否に関わりますので、裁判長から制限されてしまうことがあります。
なお、証人尋問では、情状に関する事項のみと尋問制限がかけられていますが、被告人質問では、こうした制限はかけられておらず、アリバイ関連など犯罪事実の成否に関する質問をすることができます。
刑事訴訟法第316条の37(死亡事故のご遺族又はその委託を受けた弁護士が刑事裁判で被告人質問をすることについて)
第1項(条文)
「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第311条第2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対して、その質問を発することを許すものとする。」
point:被告人に対して直接質問をすることができます
刑事裁判にご遺族が参加する大きな意義の一つとして、直接被告人に対して質問をすることができます。
しかも、証人尋問の場合と異なり、情状に関するもののみでなく、犯罪事実に関する質問をすることもできます。
従いまして、将来の民事手続における損害賠償請求の際の、慰謝料額や過失割合を意識して、被告人質問を行うことも可能です。
もちろん、それが刑事裁判と何らの関係もない事項なのであれば制限されてしかるべきですが、実際は民事の損害賠償請求と刑事手続の審理とで関わりが無い事項というのはほとんどありません。
証人尋問のパートで述べたのと同様、被告人質問も、テレビドラマのように、法廷の場で論破したり、追及したりするようなものではありません。
テレビドラマのような論破型・追及型の被告人質問をしてしまうと、裁判官の心証が悪くなってしまうこともあります。
そこで、ご遺族の方が強く望まれる場合は別として、そうでないのであれば、被害者参加代理人の弁護士がご遺族に代わって被告人質問をするのが望ましいと考えています。
なお、被告人質問の前には、公判担当検察官との打合せが行われることが多いです。
中にはご自由にどうぞと言って遺族側主導で被告人質問をさせてくれる検事もいますが、基本は事前に打合せを行います。
遺族側と検察官側とで、被告人質問で聞きたい事項を出し合って、どちらが何を質問するかについて役割分担をします。
遺族の意向を聴いた上ですべての質問を自分で行おうとする検事もいますが、検察官に丸投げするのはおすすめしません。
被害者参加代理人の弁護士は、刑事事件は当然ですが、その後の民事事件の損害賠償請求も視野に入れていますので、被害者参加代理人の弁護士が被告人質問を行うのが望ましいと考えます。
第2項(条文)
「前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。」
point:被告人質問の前に検察官に対して被告人質問事項を送付しなければなりません
被告人質問の前に被告人質問事項を検察官に申し出なければいけませんが、これは「①事故態様、②事故後の行動、③その他情状について」といった簡略的な事項の申し出で構わないとされています。
検察官によっては、より具体的に、どんな質問をする予定なのか聞いてくる人もいますし、こちらから積極的に、詳細な予定質問内容を開示することもあります。
このあたりは、事例によって戦略的に考えて良いと思います。
また、検察官が質問しようとしている具体的質問事項の紙を事前にもらえることもありますので、一度お願いしてみるといいでしょう(検察官側に提出義務はありません。)。
第3項(条文)
「裁判長は、第295条第1項、第3項及び第4項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。」
point:意見陳述に必要な事項である限り基本的には制限されません
刑事裁判の被害者参加というのは、あまり利用例がないのと、昔からある制度ではないため(平成16年の刑事訴訟法改正により新設)、裁判官も被害者参加手続に精通していないことがあります。
私も以前、被害者参加代理人弁護士として事故態様や過失の内容について被告人質問を行った際に、裁判官から「情状に関する事項ではないので、そのような質問はやめてください」と制限されたことがありました。
しかしながら、この制限は裁判官の間違えであって、証人尋問と異なり、被告人質問では情状に関する事項に限られません。
刑事訴訟法第316条の38(死亡事故のご遺族又はその委託を受けた弁護士による論告意見について)
第1項(条文)
「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」
point:検察官の論告・求刑の後に被害者遺族の側からも論告・求刑をすることができます
刑事裁判に遺族が参加する大きな意義の一つとして、遺族側からも論告・求刑意見を出すことができます。
これは情状に関する事項に限られず、死亡事故についての被告人の運転の悪質性や、当該事故の内容などについての意見をすることができます。
道路交通法規の条文解説に基づく主張を行うなどもするため、この場面では、心情意見陳述とは異なり、被害者参加代理人の弁護士が意見陳述するのが望ましいと考えています。
この遺族側の論告意見の内容が刑事裁判の判決に用いられることもあります。
なお、「訴因として特定された事実の範囲内で」という縛りがありますので、例えば、起訴状では被告人車両の速度が時速30㎞となっているのに、遺族側が被告人車両の速度は時速50㎞は出ていたなどと主張することは許されないことになります。
民事の損害賠償請求における示談交渉や裁判の場では、こうした縛りはありませんので、損害賠償請求の際に加害者車両の速度が時速50㎞は出ていたなどの主張・立証を行うことは可能です。
第2項(条文)
「前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。」
point:事前に裁判所や検察官へ提出を行います
論告意見陳述は、事前に検察官に提出しておくのが通例です。
第3項(条文)
「裁判長は、第295条第1項、第3項及び第4項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第1項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。」
point:起訴状記載の事実を超える主張を行うと制限されてしまいます
被害者参加弁護士が作成する場合には、制限されることはほとんどありませんが、民事の損害賠償請求を意識するがあまり、起訴状記載の事実を超える主張展開を明示的に行ってしまうと制限されることがありますので、制限されない程度にアピールすることが重要です。
第4項(条文)
「第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。」
point:判決に対して影響を与えます
論告意見ですので、検察官の論告と同様、証拠となることはありません。
ただし、論告意見陳述の内容が、刑事裁判の判決に直接的な影響を与えることはあります。
裁判官に対するプレゼンですので、判決書の内容に反映してもらいたいことを想定して、それを書いてもらえるような論告意見陳述を心がけましょう。
刑事訴訟法第316条の39(死亡事故のご遺族が刑事裁判に参加する際の保護について)
第1項(条文)
「裁判所は、被害者参加人が第316条の34第1項(同条5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者参加人に付き添わせることができる。」
point:心情意見陳述のときのみならず、刑事裁判の間、終始付添人をつけることができます
被害者参加する遺族について、心情意見を陳述する場面のみならず、刑事裁判の間、終始付添人をつけておくことができます。
第2項(条文)
「前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。」
point:ほとんど使うことのない条文です
想定されるような事例はほとんどなく、気にしなくてもよい条文です。
第3項(条文)
「裁判所は、第1項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不要な影響を与える恐れがあると認めるに至ったときその他その者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至ったときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。」
point:ほとんど使うことのない条文です
想定されるような事例はほとんどなく、気にしなくてもよい条文です。
第4項(条文)
「裁判所は、被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前において在席、尋問、質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護士人の意見を聴き、弁護士人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」
point:心情意見陳述のときのみならず、被告人が遺族を認識することができないよう遮蔽措置をとることができます
被告人に見られることで精神の平穏を著しく害するという場合は、被告人の前に壁(パーティションのようなもの)を立てて、被告人から遺族を見られないようにする措置をとることができます。
これは性犯罪のときなどに用いられる措置ですので、死亡事故の場合に遮蔽措置をとることはあまり多くはありません。
第5項(条文)
「裁判所は、被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」
point:傍聴人が遺族を認識することができないよう遮蔽措置をとることができます
傍聴人に見られることで精神の平穏を著しく害するという場合は、被告人の前に壁(パーティションのようなもの)を立てて、傍聴人から遺族を見られないようにする措置をとることができます。
こうした措置を取ることは、あまり多くはありません。
死亡事故(交通事故)刑事手続への被害者遺族の参加に関する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

ここでは法令の紹介のみをしておりますが、危険運転致死罪・過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪・自動車運転過失致死罪についての法定刑や加害者の刑期等に関する詳細な解説はこちらのページをご覧ください。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条(危険運転致死傷罪)
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」
1号「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
2号「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」
3号「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
4号「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
5号「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
6号「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条(危険運転致死傷罪)
第1項
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」
第2項
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。」
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条(過失運転致死傷罪)
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条(無免許運転による加重罪)
第1項
「第2条(第3号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」
第2項
「第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は6月以上の有期懲役に処する。」
第3項
「第4条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、15年以下の懲役に処する。」
第4項
「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」
死亡事故(交通事故)刑事手続への被害者遺族の参加に関する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
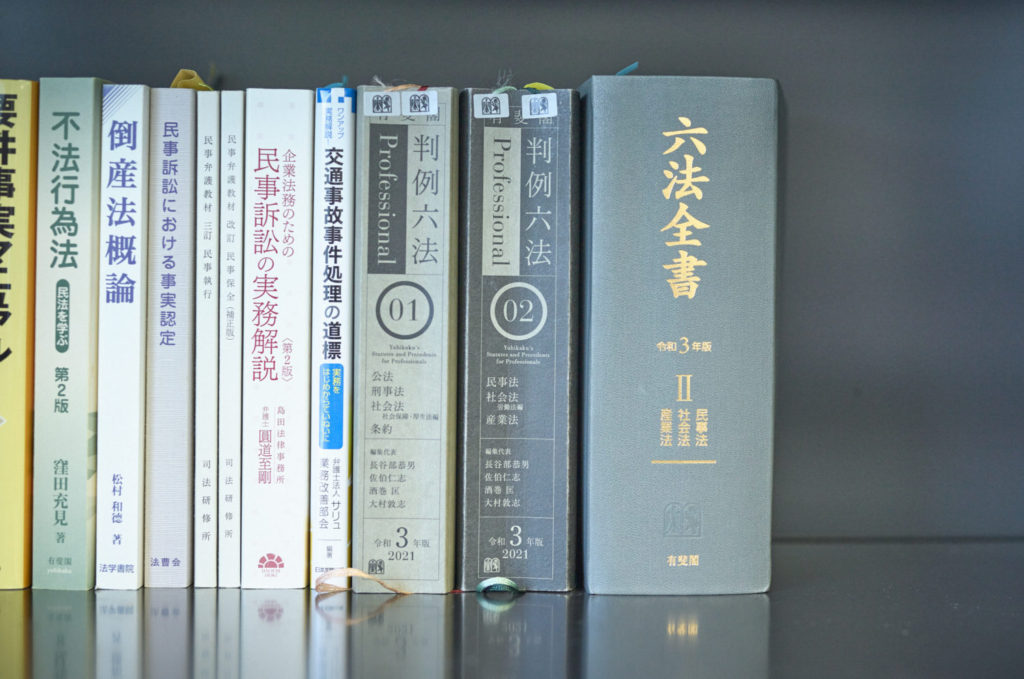
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは)
「法第3条第2項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。」
1号「自動車の安全に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととのなるおそれがある症状を呈する統合失調症」
2号「意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)」
3号「再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)」
4号「自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症」
5号「自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)」
6号「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」
死亡事故(交通事故)刑事手続への被害者遺族の参加に関する犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第1条(目的)
「この法律は、犯罪により害を被った者(以下「被害者」という。)及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにかんがみ、刑事手続に付随するものとして、被害者及びその遺族の心情を尊重し、かつその被害の回復に資するための措置を定め、並びにこれらの者による損害賠償請求に係る紛争を簡易かつ迅速に解決することに資するための裁判手続の特例を定め、もってその権利利益の保護を図ることを目的とする。」
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第2条(死亡事故遺族に対する傍聴について)
(条文)
「刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は、当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは、傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ、申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。」
point:被害者参加しない遺族関係者についても傍聴ができるよう裁判所が配慮してくれます
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第2条では、傍聴席が確保される遺族の範囲が限定されていますが(被害者参加できる者の範囲と同じ。)、実際は、裁判所から事前に傍聴席の希望席数を尋ねられ、よほど多い数でない限りは、こちらがお願いした座席分を確保してもらえます。
親族でなくとも、お亡くなりになられた被害者の友人や近所の人の傍聴席を確保してくれることもあります。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第3条(死亡事故ご遺族による刑事裁判記録の閲覧やコピー)
第1項(条文)
「刑事被告事件の係属する裁判所は、第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。」
第2項(条文)
「裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写をした裁判記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。」
point:使用目的に「民事事件」や「損害賠償請求」と記しておけば刑事裁判の資料を民事事件で使用することができます
検察の場合と異なり、刑事裁判の確定前であっても、民事利用のための資料のコピーが認められることがあります。
第3項(条文)
「第1項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写をした者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。」
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条(死亡事故のご遺族が刑事裁判に参加した際の旅費交通費や日当)
第1項(条文)
「被害者参加人(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法316条の34第1項(同条5項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。」
point:被害者参加する場合その際にかかった旅費交通費や日当が支払われます
被害者参加をする場合、その際にかかった旅費交通費や日当が支払われます。
裁判所によって、1期日ごとに用紙に記入することが求められる場合と、刑事裁判の最後にまとめて記入することが求められる場合があります。
裁判所書記官の指示に従って対応します。
第2項(条文)
「前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。」
point:日当は日額1700円・宿泊料はどこに泊まっても一律7800円(地域により8700円)となっています
政令によって、日当は日額1700円、宿泊料はどこに泊まっても一律7800円(地域により8700円)と定められています。
死亡事故刑事裁判についての弁護士小杉晴洋のコメント

以上が死亡事故遺族の刑事裁判参加に関する法令解説となります。
弁護士向け講演内容の抜粋ですので、内容がやや難しい箇所もあったかと思います。
最後までお読みいただいた方は、どうもありがとうございました。
弁護士法人小杉法律事務所では、死亡事故被害を専門に取り扱っております。
中でも、刑事裁判に対する被害者参加実績は、日本の弁護士でも有数の件数を誇っているものと自負しております。
死亡事故に関するご相談は無料にて行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
死亡事故の無料法律相談の流れはこちらのページをご覧ください。
また、その他講演実績などはこちらのページをご覧ください。
 弁護士
弁護士