その他分類
人身事故でむち打ちになったらどうする?事故から解決までの流れを弁護士が徹底解説!
2025.03.15

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- そもそもむち打ちとは?
- 事故直後にとるべき行動
- 後遺症が残った場合の対応
- 損害賠償の手続と慰謝料相場
などについて解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による人身事故解決サポートを行っております。
交通事故(人身事故)被害に遭い、お困りの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による人身事故解決サポートの詳細についてはこちら。
そもそもむち打ちとは?

むち打ちの症状
むち打ちとは、交通事故による衝撃で首がむちのようにしなることで発生する頚部外傷の総称です。
診断としては「頚部捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚部打撲」などの名称がつくことが多いです。
むち打ちの主な症状として、首や肩の痛み、背中の違和感、さらには腕のしびれや頭痛、めまいなどが発生する場合が挙げられます。
ただし、交通事故直後には自覚症状が少ないことも多く、数日後から症状が現れる場合があります。
そのため、事故に遭った際は症状がなくても早めに病院で診察を受け、診断書を取得しておくことが重要です。
交通事故でむち打ちが発生しやすい理由
むち打ちが交通事故で発生しやすい理由として、車の追突や衝撃による体の不意な動きが挙げられます。
特に後方からの追突事故では、瞬間的なエネルギーが全身に伝わるため、頚椎が大きな負荷を受けます。
車内ではシートベルトが体を固定していますが、頭(首)は固定されていないため、衝撃を受けた際に首が過屈曲・過伸展することが原因となります。
加えて、事故の際にはアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなることがあります。
そのため、事故直後には軽傷だと思ったとしても、数日後にむち打ち症の症状が出るケースが多く見られます。
交通事故にあった際は、保険会社や警察に連絡を入れるだけではなく、早期の診察が被害者にとって大切です。
むち打ちは骨折などと比較すると軽度だとみられがちですが、
後遺症が残るような場合には事故後も日常生活における支障が生じることもありますから、
しっかりと治療を受けるようにしましょう。
事故直後に取るべき行動とは?

警察への通報
交通事故が発生した場合、まずは警察に通報することが非常に重要です。
道路交通法第72条後段で、車両の運転手又は乗務員は警察に事故発生を届け出る義務があります。
また、損害賠償請求の観点から見ても、警察への通報をしていない場合には、事故発生や事故態様についての証明が難しくなってしまいます。
通報の際には、事故の状況を冷静に伝え、自身や他の被害者の怪我の有無を明確に説明しましょう。
病院での診断書取得の重要性
むち打ちなどの症状がある場合、速やかに医療機関で診察を受けることが重要です。
交通事故によるむち打ちは、事故直後には痛みや違和感が現れにくいこともありますが、後日症状が悪化することが少なくありません。
事故日から初診日に間が空きすぎていると、加害者側保険会社などから、
- 「本当に今回の事故で負った怪我なのか?」
という疑念を抱かれ、治療費の対応を拒否されたり、慰謝料の支払を拒否されたりというリスクが生じてしまいます。
ご自身が気づいていない症状に気づくきっかけになることもありますので、
お身体のためにも損害賠償請求のためにも速やかに受診をするようにしましょう。
また、医療機関を受診した際は診断書を取得しておきましょう。
診断書は医師が今回の事故により受傷したという事実や、その受傷の程度について証明をしてくれる書類ですから、
加害者側保険会社に対して損害賠償請求をしていくうえで極めて重要な証拠になります。
そして、次に出てくる物損事故から人身事故に切り替える際にも必要となります。
物損事故から人身事故に切り替える場合の手順
事故後に最初は物損事故として処理されたものの、後からむち打ちなどの怪我が発覚することがあります。
この場合、人身事故への切り替えを速やかに行うことが可能です。
切り替えるためには、まず医療機関で診断を受け、診断書を取得した上で警察署に届け出を行います。
その際、診断書を警察に提出し、交通事故証明書の訂正を依頼することになります。
この物損事故/人身事故の区分は、警察における処理の区分ですから、
損害賠償請求において大きな意味を持つというわけではありません。
しかし、物損事故扱いから人身事故に切り替える場合には、若干のメリット・デメリットがあります。
まず1つ目のメリットが、警察・検察の捜査がより詳しく行われるようになる点です。
物損事故扱いということは翻って言えば人的損害が発生していないという認識になっているということですから、
刑事罰に該当する可能性がなく、検察への送致はされません。
警察で物件事故報告書という書類を作成して捜査が終了します。
一方で人身事故に切り替えた場合には、過失運転致傷罪などに該当する可能性が生じるため、
警察での捜査もより詳細に行われますし、検察に送致され、そこでも捜査がされることになります。
供述調書の作成なども行われることになります。
物件事故報告書でも過失割合の検討は可能ですが、より詳細に捜査された記録の方が綿密な検討が可能ですし、
加害者側の供述調書の中でわき見運転をしていたなどの話が出てくれば、それをもとに過失割合を有利に修正することもできます。
また、人身事故扱いの場合の捜査記録では、事故発生時の両者間の距離や、事故の衝撃でどれくらい吹き飛ばされたかなども記載されます。
むち打ちで後遺障害等級の認定を得るためには、事故の衝撃の大きさの証明が重要になる場合があるため、後遺障害等級認定を考えても有用です。
2つ目のメリットが、「事故の軽微さを推認されない」ことです。
事故発生時に被害者が救急搬送された場合、当然に人身事故になるでしょう。
逆に、物件事故として処理されているということは、その場では病院に行く必要があるとは認識されない程度の事故態様だったと推認する要素になります。
後遺障害等級の認定は自賠責保険を通じて損害調査事務所に対して申請をすることになりますが、
その際に「人身事故証明書」が必要となります。
人身事故証明書が発行されていない場合≒物件事故扱いで処理されている場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することになります。
もちろんむち打ちは事故から数日経ってから症状が出ることも多い傷病ですから、
人身事故証明書が入手できなかったからと言って即ち事故により負った怪我が軽いと断定されるわけではありませんが、
後遺障害等級認定には若干程度影響する可能性もあります。
症状が重い場合には後遺症が残る可能性もありますから、積極的に人身事故への切り替えを検討しておきましょう。
一方で人身事故への切り替えはデメリットもあります。
それは、被害者側にも過失がある場合には行政処分の対象となることです。
自動車対自動車の事故などで、被害者側にも過失が認められる場合には、被害者にも注意義務違反があるということになります。免許証の点数が引かれる可能性も生じます。
メリットとデメリットを比較衡量しながら判断をする必要がありますから、
適切な対応のためにも、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
むち打ちに対する適切な治療

むち打ちの一般的な治療法とは?
むち打ちの治療は、主に頚椎へのダメージを軽減するための保存療法が中心となります。
交通事故によるむち打ちでは整形外科での診断が重要で、多くの場合、痛みや炎症を抑えるための薬物療法、温熱療法、物理療法などが用いられます。
また、症状が強い場合には、頚椎を安定させるための頚椎カラーの装着が指示されることがあります。
これにより頚部が保護され、治癒を促進することが期待されます。
さらに、むち打ちは初期症状が軽度であっても、放置すると症状が悪化するリスクがあるため、
診断書を取得し、継続的な治療を受けることが大切です。
損害賠償請求の観点からみた適切な治療
お身体が最も大切ですから、ご自身に合う治療が最も良いのは大前提です。
また、お仕事の関係などもあり、通院をしたくてもできないというご事情もあるでしょう。
そのうえで、損害賠償請求の観点、とりわけ後遺障害等級の認定という観点からみて推奨される治療があります。
まず第一に整形外科への通院を行うことです。
後遺障害等級の認定を行う自賠責損害調査事務所も、裁判所も、むち打ちの治療に当たっては整骨院より整形外科の通院を重視します。
整骨院への通院がマイナスになるというわけではありませんが、
整形外科への通院がなければ後遺障害等級はまず認められません。
最低でも月1回は整形外科へ通院しましょう。
お仕事の関係で整形外科への通院が難しい場合には、その旨を主治医に伝えたうえで、整骨院への通院に対して指示や承諾を得ておくようにしましょう。
第二に、週2~3回の通院を6か月間行うことです。
むち打ちで後遺症が残る場合、認定される可能性がある後遺障害等級は第12級13号か第14級9号になります。
第12級13号は、痛みやしびれが持続的に残ることが医学的に証明できるものが該当し、
第14級9号は、痛みやしびれが持続的に残ることが医学的に説明できるものが該当します。
後遺症は、原則として将来にわたって残り続けるものでなければなりませんから、
ある程度の期間治療を続けたうえでもなお症状が残っている場合にしか認められません。
このある程度の期間治療を続けたというために必要な治療期間・頻度が、
6か月間週2~3回の通院を続ける、というものになります。
むち打ちで後遺障害等級認定を得ようとする場合には、上のような通院治療を行う必要があります。
ただし、通院を継続すべきなのはあくまで実際に痛みが残っている場合のみです。
後遺症が残っていないのに後遺障害等級認定を得るであったり、慰謝料額を増やす目的で通院を継続したりしていると、治療の必要性が否定され、治療費だけが余計にかかるリスクもあります。
- 関連記事:むち打ち徹底解説
後遺症が残った場合の対応
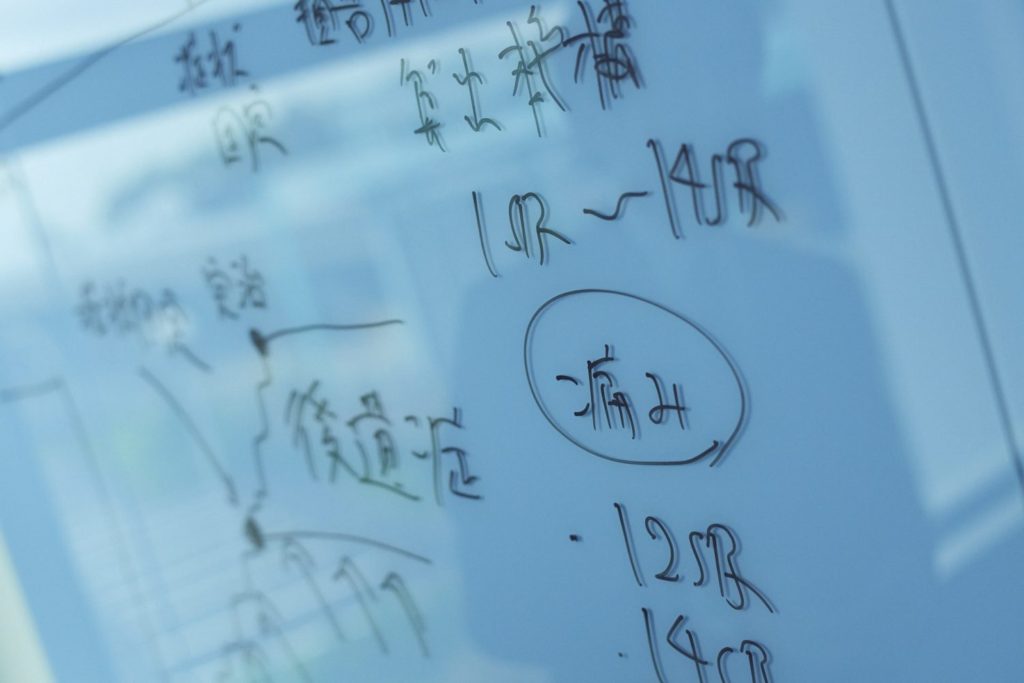
むち打ちによる後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺症慰謝料や後遺症逸失利益の請求が可能になります。
むち打ちの場合に認定される可能性があるのは、先ほども見た第12級13号か第14級9号です。
むち打ちによる後遺障害等級の認定にあたっては、大きく分けて以下の6つのポイントがあります。
- 常時痛であること
- 事故態様の大きさ
- 自然な症状推移
- 適切な治療
- 他覚的所見の有無
- 整形外科への通院
第12級13号と第14級9号の違いは、医学的に証明できるか、説明がつくかです。
痛みやしびれといった症状は、被害者本人には分かりますが、他人から見て一目でわかるような症状ではありません。
ですから、他人から見ても証明できるような証拠が必要であり、それが「他覚的所見」です。
重度のむち打ち症の場合、事故の衝撃で椎間板ヘルニアが生じ、神経を刺激してしまうことがあります。
MRI画像などで神経が刺激されている所見が確認できれば、医学的に証明ができるということで、第12級13号の認定がされます。
しかし、この第12級13号の認定は、一見して分かるようなかなりひどい態様のヘルニアでなければなかなか難しいです。
一方で第14級9号の認定を目指す場合、第12級13号の認定に必要なほどの他覚的所見は求められません。
しかし、「確かにこれは痛みやしびれが残存していそうだな」と説明がつくくらいの情報が必要になります。
それが上に挙げた他覚的所見以外の5つの要素です。
まずそもそも常時痛でなければ後遺症として認められません。
交通事故被害に言う後遺症は、労働能力の喪失を前提としているため、たまに痛い程度では労働能力に影響はないと判断され、後遺症とはなりません。
そして、事故態様が大きければ残る症状も大きいと言えそうですし、
適切な治療(期間・内容・頻度)が行われていたにもかかわらず、症状が残ってしまったとなると、たしかに後遺症だという判断がしやすくなります。
第14級9号の認定はこういった細かな事実の積み重ねが必要になります。
後遺症が残る可能性がある場合には、
治療期間中から週2~3回の整形外科への通院を6か月間行うことを意識しましょう。
また、MRIの撮影を事故直後と症状固定直前に行っておくことで、
事故によりヘルニアが生じ、それが症状固定時にも残存しているということを示すことができます。
6か月の通院に満たないタイミングで加害者側保険会社から治療費一括対応の打ち切りを言われた場合には、
主治医が治療の継続が必要と言っているかどうかを確認したうえで、治療費対応の延長を交渉するべきです。
それが難しい場合には、治療費分損をするリスクが生じますが、自費での通院を検討することもあり得ます。
後遺障害等級の認定は受け取れる示談金額に大きく影響しますから、
交通事故被害を専門とする弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
損害賠償と慰謝料の手続き・相場

むち打ちの慰謝料相場
むち打ちによる慰謝料は、被害者の怪我の程度や通院期間、後遺障害の有無によって大きく異なります。
具体的には、治療が終了するまでの期間に基づき入通院慰謝料が支払われます。
例えば、1か月間の通院で約19万円、6か月で約89万円が相場とされています。
後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料の対象となります。
14級に該当する場合の相場は約110万円、12級では約290万円程度とされています。
また後遺障害等級が認定されると、後遺症が残ってしまったことにより将来にわたって発生する収入減である逸失利益についても請求が可能になります。
後遺障害等級が認定されるか(何級が認定されるか)によって賠償金額は大きく変わりますから、
後遺症が残る場合には適切な後遺障害等級の認定を得ることが重要です。
示談交渉を有利に進めるためのポイント
示談交渉は、治療終了後、または後遺障害等級の認定後に加害者側保険会社が賠償金額の提示をしてくることで始まることが多いです。
この加害者側保険会社の提示が、被害者側から見て妥当であることはほとんどありません。
なぜなら、加害者側保険会社は被害者に支払う保険金額が少なければ少ないほど得をする立場にあるからです。
被害者側として示談交渉を有利に進めるためには、まずは加害者側保険会社の提示が妥当な金額かどうか、
適正な基準での算定がされているかを確認する必要があります。
そのうえで、妥当ではない項目(休業損害、逸失利益、慰謝料など)がある場合には、
証拠を提示しつつ適正な基準に基づいた計算を行うことで、金額の交渉をする必要があります。
この妥当な金額かどうかの見極めと、適正な基準での計算については、
交通事故を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。
人身事故被害に遭い、むち打ちでお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
 弁護士
弁護士