脳損傷 神経症状
【脳挫傷の後遺症】医師監修記事|後遺症被害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、【脳挫傷の後遺症】について、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)監修のもと整理しております。
脳挫傷とは

(以下「標準脳神経外科学」(医学書院)267頁及び276頁参照)
脳損傷のうち、脳の損傷が限局的で脳全体への波及が少ないものを脳挫傷(局所性脳損傷)と言います。
他方、脳の広範位にわたる損傷を起こした状態がびまん性軸索損傷と呼ばれます。
脳挫傷の後遺症は交通事故等の外傷が契機となることが多いです

(以下「標準脳神経外科学」(医学書院)266~267頁及び275頁参照)
脳挫傷は穿通外傷のように外力が極めて限局的に加わってできる場合もありますが、多くの場合は頭部に加速あるいは減速の衝撃が生じて発生します。
また、頭部を強打したときに生じる脳挫傷には、直撃損傷と対側損傷があります。
外力が作用点の直下に発生する脳損傷を直撃損傷、慣性力によって外力作用点の対極に発生するものを対側損傷といいます。
対側損傷がみられる場合、対側の方が脳の損傷が大きいことが多いと言われます。
前頭部の受傷では、ほとんどが前頭葉への直撃損傷であり、対側損傷は少ないです。
後頭部や頭頂部の受傷では、直撃損傷は少なく、前頭葉や側頭葉先端部に対側損傷がみられます。
いずれの場合も後遺症が残存してしまうことが多くなっています。
→穿通外傷、加速あるいは減速の衝撃等の具体的な説明は脳挫傷一般について整理したこちらの記事でご確認ください。
脳挫傷の後遺症の内容:損害賠償請求視点
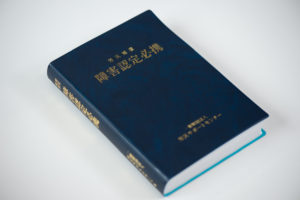
脳挫傷の後遺症は上述のとおり、交通事故等の外傷を契機として生じることが多いです。
また、本記事は医師監修記事となっておりますが、執筆者は後遺症を専門に扱う弁護士ですので、以下では、交通事故による外傷を契機として脳挫傷の後遺症を残してしまった場合、その後遺症の内容や程度に応じて、どのような後遺障害等級が認定されるのかを中心に解説させていただきます。
なお、脳挫傷による後遺症で性格の変化が生じてしまった場合、脳挫傷による後遺症と前頭葉の関係、脳挫傷の後遺症が数年後に発覚した場合については、下記の記事にて詳細に解説しておりますので、そちらをご覧ください。
→脳挫傷の後遺症が数年後に発覚した場合についての記事はこちら
脳挫傷の後遺症:後遺障害等級一般論
自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。
同じ事故で受傷した脳損傷等で身体性機能障害と高次脳機能障害の両方が発生することもありえますが、その場合はそれらの障害による就労制限や日常生活制限の程度に応じて総合的に等級判断がなされます。
他方、脳損傷により感覚器などに障害を生じた場合で、その障害について、該当する等級(相当等級を含む。)があるときは、その該当等級を認定することになり、そのほかに脳の障害があれば、両者を併合することができます。
下記のとおり、第1級から第14級まで認定の幅は広くあるのですが、どうしても就労できない、あるいは日常生活に著しい支障をきたす等の訴えがあったとしても、神経系統の障害が医学的に証明されたもの(他覚所見によって証明されたもの)でなければ、非器質性精神障害の基準により等級評価を行う場合を除き、別表第二第12級以上の等級の適用はできないとされていますので、ご留意ください。
他方で、たとえ自覚症状の訴えが軽い場合であっても、CT・MRI等で異常が認められたり、脳波に異常が認められる場合には、医学的に証明されたもの(他覚所見によって証明されたもの)として別表第二第12級の評価が可能だとされています。
脳挫傷のCT等の画像所見について
上記のとおり、脳挫傷の後遺症において、12級以上の後遺障害等級が認定されるためには、他覚所見による証明が必要とされています。
他覚所見というのは、簡単に言うと「目に見える根拠」ということであり、典型例としてはCT等の画像所見が挙げられます。
頭部CT画像での経時的な観察が重要です。
脳挫傷の受傷部位には点状出血がみられます。
CTでは低吸収域(脳浮腫)の中に高吸収域(小出血)が散在し、ごま塩状の所見がみられ、典型的な脳挫傷の画像所見と言われます。
点状出血は集合してみられることが多いですが、時間経過とともに増大・融合して血腫になります。また、浮腫も生じ増大するため、周囲の脳を圧迫します。
こうした画像所見が認められると、脳挫傷の後遺症として無症状であったとしても、後遺障害等級12級13号の認定が確約され、それ以上の等級評価は、被害者に残存する後遺症の内容の酷さから判定されることになります。
※高吸収域・低吸収域
頭部CT画像検査では、周囲の正常組織と比較して、高吸収域は白く、低吸収域は暗く描出されます。
急性期の出血は高吸収になる代表的疾患ですが、経時的な血腫の自然吸収に伴い低吸収域になっていきます。
※脳浮腫
脳組織の水分量が増加し、容積が増大している状態を指します。脳挫傷等が原因で生じます。
水分量が多くなると、CT画像上は低吸収になり、暗く描出されます。
脳挫傷の後遺症①:高次脳機能障害
脳挫傷によって高次脳機能障害となってしまった場合の後遺症評価は、次のような目安でなされます。
なお、高次脳機能障害に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。
また、高次脳機能障害の等級認定に必要な検査や書式等はこちらの記事で整理しています。
| 別表第一第1級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」をいい、「身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの」もこれにあたります。 |
| 別表第一第2級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」をいい、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」がこれにあてはまります。 |
| 別表第二第3級3号 | 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」をいい、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第5級2号 | 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」をいい、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第7級4号 | 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」をいい、「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第9級10号 | 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」がこれに該当します。 |
脳挫傷の後遺症②:身体性機能障害
脳挫傷によって身体性機能障害となってしまった場合の後遺症評価は、次のような目安でなされます。
| 別表第一第1級1号 | 高度の四肢麻痺、中程度(常時介護)の四肢麻痺、高度(常時介護)の片麻痺 |
| 別表第一第2級1号 | 中程度(随時介護)の四肢麻痺、高度の片麻痺 |
| 別表第二第3級3号 | 中程度(除く介護)の四肢麻痺 |
| 別表第二第5級2号 | 軽度の四肢麻痺、中程度の片麻痺、高度の単麻痺 |
| 別表第二第7級4号 | 軽度の片麻痺、中程度の単麻痺 |
| 別表第二第9級10号 | 軽度の単麻痺 |
| 別表第二第12級13号 | 軽微の四肢麻痺、軽微の片麻痺、軽微の単麻痺 |
四肢麻痺とは左右の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。
片麻痺とは一側の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。右上肢と右下肢、あるいは左上肢と左下肢の2種です。
単麻痺とは、左右の上肢と下肢のどれか1肢にのみ麻痺が出ている場合を言います。
「高度の麻痺」には次のようなものが該当します。
| ①完全強直またはこれに近い状態にあるもの |
| ②上肢においては、3大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないものまたはこれに近い状態にあるもの |
| ③下肢においては、3大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないものまたはこれに近い状態にあるもの |
| ④上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した1上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの |
| ⑤下肢においては、随意運動の顕著な障害により、1下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの |
「上肢」とは肩~手指まで、「下肢」とは股関節~足指までを指し、3大関節というのは、上肢だと肩、肘、手首、下肢だと股関節、膝関節、足首のことを指します。
以下、この点は共通です。
→上肢下肢や3大関節がどこを指すか等はこちらの記事でも整理しています。
「中等度の麻痺」とは、具体的には次のようなものとされています。
| ①上肢においては、障害を残した1上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないものまたは障害を残した1上肢では文字を書くことができないもの |
| ②下肢においては、障害を残した1下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないものまたは障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの |
「軽度の麻痺」の具体例としては、次のようなものがあります。
| ①上肢においては、障害を残した1上肢では文字を書くことに困難を伴うもの |
| ②下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した1下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いものまたは障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの |
「軽微な麻痺」の具体例としては、次のようなものがあります。
| ①軽微な随意運動の障害または軽微な筋緊張の亢進が認められるもの |
| ②運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね1上肢または1下肢の全域にわたって認められるもの |
脳挫傷の後遺症③:感覚器等の機能障害
脳挫傷によって感覚器の機能が障害されてしまった場合には、感覚器の機能障害に準じて後遺症評価がなされることになります。
脳神経損傷によって生じる場合と同様の区分になりますので、脳神経損傷を合併することの多い頭蓋底骨折の記事にて感覚器等の機能障害の詳細を記載しております。
→感覚器等の機能障害については頭蓋底骨折の記事をご覧ください。
脳挫傷の後遺症④:外傷性てんかん
脳挫傷によっててんかん発作が生じてしまった場合の後遺症評価は、次のような目安でなされます。
| 別表第二第5級2号 | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が『意識障害の有無を問わず転倒する発作』または『意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作』(以下『転倒する発作等』といいます。)であるもの |
| 別表第二第7級4号 | 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの、または転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの |
| 別表第二第9級10号 | 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、または服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
| 別表第二第12級13号 | 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |
上記の後遺障害等級5級2号の頻度を超えて1ヶ月に2回以上の発作がある場合には、通常、高度の高次脳機能障害を伴うので、脳の高次脳機能障害にかかる別表第二第3級以上の認定基準により後遺症評価を行うとされています。
なお、ここでいう「転倒する発作」の例としては、次のようなものがあります。
① 意識消失が起こり、その後ただちに四肢等が強くつっぱる強直性のけいれんが続き、次第に短時間の収縮と弛緩を繰り返す間代性のけいれんに移行する強直間代発作
② 脱力発作のうち、意識は通常あるものの、筋緊張が消失して倒れてしまうもの
また、「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」の例としては、「意識混濁を呈するとともに、うろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し、発作中は周囲の状況に正しく反応できないもの」が挙げられます。
→外傷性てんかんで必要な検査等、詳細はこちらの記事をご覧ください。
脳挫傷の後遺症⑤:失調・めまい・平衡機能障害
脳挫傷によって失調、めまい及び平衡機能障害となってしまった場合の後遺症評価は、次のような目安でなされます。
| 別表第二第3級3号 | 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服すことができないもの |
| 別表第二第5級2号 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |
| 別表第二第7級7号 | 中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般人の1/2程度に明らかに低下しているもの |
| 別表第二第9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
| 別表第二第12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他の平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
| 別表第二第14級9号 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見がみとめられないものの、めまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの |
脳挫傷の後遺症⑥:遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、脳挫傷などのため昏睡状態に至り、生命の危機を脱したのちに開眼できる状態にまで回復したものの、周囲との意思疎通能力を喪失した状態のことを言います。
遷延性意識障害となってしまった場合には、常時介護が必須となりますので、後遺症評価としては、2以下の後遺障害等級が認定されることはなく、別表第一第1級1号の後遺障害等級が認定されることになります。
脳挫傷の後遺症⑦:頭痛
脳挫傷によって頭痛の後遺症が残ってしまった場合の後遺障害等級認定については、次のような目安でなされます。
| 別表第二第9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 別表第二第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 別表第二第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
脳挫傷による後遺症のまとめ

交通事故等の頭部外傷で生じる脳挫傷は、脳損傷の一形態ですが、損傷部位や程度によって様々な症状が発現しえて、認定可能性のある後遺障害等級も様々です。
後遺症慰謝料・後遺症逸失利益や将来治療費・将来介護費などの損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うためには、受傷の態様を正確に把握し、残存した後遺症についての立証資料を適切に収集・検討していく必要があります。
脳挫傷による後遺症の場合、損害賠償金額が億単位となることも多いので、適切な損害賠償を受けるためにも、後遺症専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人小杉法律事務所では無料相談を実施しておりますので、是非ご活用ください。
脳挫傷により後遺症を負った被害者の弊所解決事例
→脳挫傷痕から12級13号の後遺障害認定を受けた被害者について異議申立てにより併合5級の認定を獲得した示談解決事例
→交通事故による脳挫傷から高次脳機能障害となってしまい約2.5億円の損害賠償金額にて解決した裁判事例
 弁護士
弁護士