慰謝料
被害者必見!弁護士基準で計算するもらい事故の慰謝料とは?
2025.03.31

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- もらい事故の基礎知識
- 弁護士基準での慰謝料計算
- もらい事故の慰謝料を最大化する方法
- もらい事故の慰謝料に関連する注意点
などについて解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による慰謝料(賠償金)無料査定サービスを行っております。
もらい事故被害に遭い、ご自身が受け取れる慰謝料(賠償金)の額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による慰謝料(賠償金)無料査定サービスの詳細についてはこちら。
もらい事故の基本知識

もらい事故の定義とは?
もらい事故とは、交通事故の中でも被害者側に過失がない、または極めて低い事故を指します。
例えば、信号待ち中に後ろから車が追突してきた追突事故や、赤信号を無視した車との衝突事故などが典型例です。
被害者に過失がない場合、基本的には損害賠償や慰謝料を満額請求することが可能です。
しかし、加害者側保険会社から提示される金額が適切なことはほとんどないため、しっかりと確認することが重要です。
もらい事故で被害者が受け取れる賠償金の種類
もらい事故の被害者が受け取れる賠償金には、大きく分けて、
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
の3つがあります。
積極損害とは、事故に遭ったことで余計に支出せざるを得なくなった損害です。
代表的なものとしては、治療費や通院交通費が挙げられます。
積極損害は原則としてまさに発生した実費としての損害を請求することになりますから、
領収証などを保管しておくことが重要になります。
消極損害は、事故に遭わなければ得られていたはずなのに、事故に遭ったせいで得られなくなった損害です。
休業損害と逸失利益の違いは、症状固定以前か以後かです。
症状固定以前に発生した休業損害(事故に遭ったことで入通院のために仕事を休まざるを得ず、収入が減少した損害)については、
現に発生している収入減を請求できるため、比較的金額の算定がしやすいです。
一方で後遺症が残ってしまったことにより、将来にわたって収入が減少する(労働能力を喪失する)損害をいう逸失利益については、
将来の話をすることになるため、いわばフィクションの話になります。
そのような状況の中でも可能な限り蓋然性のある金額を算出できるように努めていく必要があります。
慰謝料は、事故被害に遭ったことによって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償です。
慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」というかたちで、被害者が受けた被害の程度などによって分かれます。
賠償金は、慰謝料をはじめとする、今回のもらい事故で受けた被害全体に対して支払われるお金を指しており、
厳密には慰謝料と賠償金は別ものになります。
もらい事故が発生した場合の一般的な対応
もらい事故の場合、被害者側の過失はほとんどありませんから、基本的には加害者側任意保険会社が治療費の一括対応を行ってくれることが多いです。
事故直後は速やかに警察に連絡し、加害者から本人や任意保険会社の連絡先の聞き取りをしましょう。
そして、できる限り早く、遅くとも1週間以内には医療機関を受診するようにしましょう。
もらい事故の中でも典型的といえる追突事故の場合、事故直後には気づいていない頚部痛や腰部痛(いわゆるむち打ち)の症状が出てくることがあります。
お身体の状態を早期に確認しておくことが、適切な治療に繋がることはもちろんですが、
事故から初診日までの期間が空いてしまうと、加害者側保険会社から「この怪我は本当に今回の事故によって負った怪我なのか?」という疑念を持たれるリスクが生じてしまいます。
事故直後は大丈夫と思っても、念のため医療機関を受診することをお勧めします。
また、この時診断書の作成を依頼しておくことで、事故直後は物件事故扱いで処理されていた場合にも、
速やかに人身事故への切替が可能になります。
人身事故への切替を検討する場合には、診断書の作成を行っておきましょう。
- 関連記事:交通事故後に病院で必ず診察を受けるべき理由とは?【弁護士解説】
- 関連記事:交通事故の診断書:被害者必見!その重要性と取得のポイント
- 関連記事:弁護士が解説!物損事故から人身事故へ切り替える際の手続とポイント
弁護士基準(裁判基準)での慰謝料計算とは?

弁護士基準(裁判基準)の特徴
弁護士基準(裁判基準)は、その名のとおり弁護士や裁判所が用いる基準です。
そもそも、「なぜ交通事故被害に遭ったら慰謝料の請求ができる」のでしょうか。
それは、法律でそう規定されているからです。
民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
自動車損害賠償保障法第3条「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」
これらの法律で規定されているからこそ、
交通事故を起こしてしまった加害者は、被害者に対して発生させた損害を賠償する責任を負い、
逆に被害者は損害の賠償をしてもらう権利を得られるということになります。
では、その権利が具体的にいくら発生しているのかについて、裁判所は法律に基づいた認定を行います。
その認定の積み重ねによりつくられたのが弁護士基準(裁判基準)であり、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)というわけです。
この弁護士基準(裁判基準)の最大の特徴は、
裁判所が、加害者から被害者に対して支払われるべき損害賠償額として認定した金額、つまり被害者からみれば最も高額かつ適切な金額をベースとした基準であるという点です。
後述する自賠責基準や任意保険基準と比較しても、金額の差が大きく、
弁護士基準(裁判基準)に基づく請求を行うことで大きな増額が期待できる場合があります。
弁護士基準と自賠責基準・任意保険基準の違い
交通事故の慰謝料を計算する際に用いられる基準には主に、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準の3種類があります。
自賠責基準とは自賠責保険金の支払基準「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」のことです。
交通事故被害者が、迅速かつ平等に保険金を受け取ることができる反面、金額としては3つの基準の中で最も低額です。
一方、任意保険基準は各保険会社が独自に算出している基準です。
任意保険は、各々が自賠責保険の上乗せとして契約している保険です。
したがって、任意保険会社の基準が自賠責基準を下回ることはありません(自賠責基準を下回るのであれば保険契約を締結している意味がなくなってしまいます。)。
一方で任意保険会社は被害者に支払う慰謝料額が少なければ少ないほど自社の利益を大きくすることができます。
ですから、任意保険基準はどの会社であっても、自賠責基準と同じかやや高いくらいに収まります。
この任意保険基準で計算された慰謝料額が被害者側からみて適切であることはほとんどありません。
これに対して弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、慰謝料として最も適切かつ高額な金額を算出します。
このような違いから、被害者が正当な慰謝料を得るためには弁護士基準を採用することが重要です。
- 関連記事:交通事故被害者が知っておくべき自賠責保険の慰謝料の基準
- 関連記事:両方もらえる!?交通事故慰謝料の自賠責と任意保険を賢く活用する方法
- 関連記事:交通事故の慰謝料、弁護士基準でいくらもらえるのか?徹底解説
弁護士基準での入通院慰謝料の相場と計算方法
弁護士基準を用いた場合の入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基に計算が行われます。
例えば、「むちうち」のケースでは、通院3か月で約53万円、6か月で約89万円が相場とされています。
仮に自賠責基準(日額4300円×実入通院日数の2倍か入通院期間のどちらか短い方)で計算した場合には、
通院3か月で20万6400円程度、通院6か月で41万2800円程度になりますので、
弁護士基準での計算が重要であることがお分かりいただけると思います。
弁護士基準での後遺症慰謝料の相場
後遺症慰謝料は、原則として認定された後遺障害等級に応じて金額が決まります。
この原則自体は、自賠責基準でも、任意保険基準でも、弁護士基準でも変わりませんが、
各後遺障害等級が認定された場合の金額が変わってきます。
例えば後遺障害等級第14級が認定された場合の自賠責基準での後遺症慰謝料は32万円ですが、
弁護士基準では110万円という具合です。
後遺症慰謝料一つを取ってみても、弁護士基準での請求の重要性がお分かりいただけると思います。
以下が、各後遺障害等級が認定された場合の弁護士基準での後遺症慰謝料の目安です。
- 後遺障害等級第1級:2800万円
- 後遺障害等級第2級:2370万円
- 後遺障害等級第3級:1990万円
- 後遺障害等級第4級:1670万円
- 後遺障害等級第5級:1400万円
- 後遺障害等級第6級:1180万円
- 後遺障害等級第7級:1000万円
- 後遺障害等級第8級:830万円
- 後遺障害等級第9級:690万円
- 後遺障害等級第10級:550万円
- 後遺障害等級第11級:420万円
- 後遺障害等級第12級:290万円
- 後遺障害等級第13級:180万円
- 後遺障害等級第14級:110万円
弁護士基準での死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料についても弁護士基準が最も高額になります。
- 被害者が一家の支柱と評価される場合の死亡慰謝料:2800万円
- 被害者が母親、配偶者と評価される場合の死亡慰謝料:2500万円
- 被害者がその他(独身の男女、子供、幼児等)と評価される場合の死亡慰謝料:2000万円~2500万円
この金額には、被害者本人の慰謝料だけでなく、被害者を失ったことにより近親者が受けた苦痛に対する慰謝料も含まれています。
ただし、これは一応の目安であって、具体的な斟酌事由によって増減されるべきであるとされています。
もらい事故の慰謝料を最大化する方法
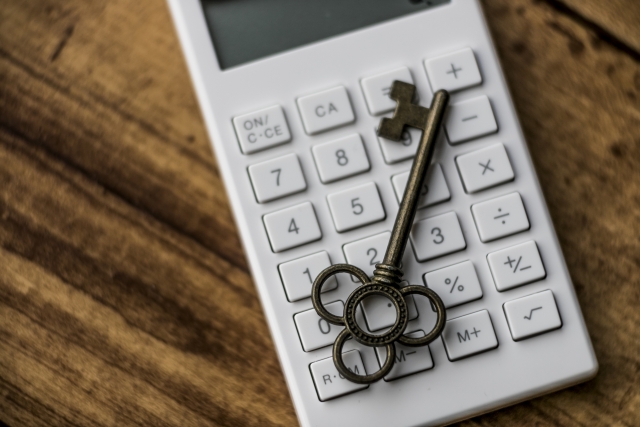
証拠収集の重要性
もらい事故の慰謝料を最大化するために必要なのは証拠です。
示談交渉が決裂した場合には最終的には裁判所の判断を仰ぐことになりますが、
裁判所は証拠に基づいた判断を行います。
ですから、受けた精神的苦痛の大きさを示す証拠をいかに用意して提出できるかによって、
受け取れる慰謝料の金額が変わってきます。
入通院慰謝料の場合には、入通院や手術が大変であったことを示す証拠(入通院日数の記録や手術回数の記録など)が重要となります。
後遺症慰謝料の場合には、認定された後遺障害等級自体がまず大きな証拠になります。
そのうえで、実際に日常生活における支障の大きさを動画で撮影したり、後遺症の残存により断念した夢の大きさを示す陳述書を作成したりといった証拠が重要となります。
死亡慰謝料の場合も、被害者が生前どのような方であったか、近親者の方が被害者を失ったことでどれだけの苦痛を受けたかを示す陳述書が大きな証拠となります。
慰謝料以外の費目であっても、証拠は極めて重要です。
交通事故を専門とする弁護士に依頼すると何が変わるかというと、
交通事故を専門とする弁護士は、裁判所がどのような証拠に基づいてどのような判断を下すかに関する知識が豊富なため、
治療中や示談交渉の時点から、適切な証拠収集に関するアドバイスをしてくれます。
交通事故専門弁護士に依頼することで、適切な証拠収集をしながら進めていくことができ、慰謝料の金額を大きくすることができます。
保険会社との交渉で注意すべきポイント
もらい事故における保険会社との交渉では、被害者が提示された金額をそのまま受け入れないことが重要です。
保険会社は通常、自賠責基準や任意保険基準を基に低めの慰謝料を提示してくることが多いため、適切な基準である弁護士基準との差に注意する必要があります。
また、交渉の際は冷静かつ論理的に対応し、不公平な条件を受け入れない姿勢を保つことが重要です。
弁護士に相談することで、より有利な条件で交渉を進められる場合もあります。
弁護士特約の活用方法
弁護士特約を活用することで、交通事故に関連する慰謝料や損害賠償請求を有利に進めることが可能です。
弁護士特約とは、加入している任意保険に付帯されていることがある特約で、その費用を保険会社が負担します。
これにより、被害者は実質的な費用負担を気にせず弁護士に依頼できます。
もらい事故(10対0事故)の場合は被害者側の保険会社が示談代行を行ってくれないため、
弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼は非常に有用です。
示談交渉を有利に進めるためのコツ
示談交渉を有利に進めるためには、専門家のアドバイスを受けつつ、準備をしっかりと進めることが重要です。
まず、事故の詳細や怪我の状況に関する証拠を揃えることから始めます。
また、示談書や提示された条件の内容を慎重に確認し、すぐにサインをしないことが大切です。
もらい事故の慰謝料に関連する注意点

もらい事故の示談成立までの流れ
もらい事故の示談成立は、被害者が加害者側(加害者側保険会社)と慰謝料やその他の賠償金について合意することで成立します。
事故発生から示談成立までは、一般的には次のような流れで進むことになります。
まずもらい事故に遭ったら、速やかに警察に連絡し、捜査を行ってもらうことになります。
もらい事故の場合は被害者側の過失割合は0になるので、あまり問題にはなりにくいですが、警察には自分が把握している事故状況を正確に伝えましょう。
その後はできる限り速やかに病院での診察を受け、そこから治療を続けていくことになります。
治療がある程度終了した段階で、完治か症状固定かに進むことになります。
完治の場合はその後すぐに、症状固定の場合には適切な後遺障害等級が認定された後に、加害者側と実際の損害額についての交渉が始まります。
この加害者側との示談交渉においては、加害者側から提示される金額が被害者から見て妥当であることはほとんどなく、
弁護士基準に基づいた適切な請求を行う必要があります。
お互いが納得できるラインまで金額が上がった場合には示談書を取り交わし、示談締結ということになります。
過失割合がゼロであっても起こりうるトラブル
もらい事故は、被害者に過失がないケースが多いですが、それでもトラブルが発生する可能性があります。
その一例として、相手の保険会社が慰謝料を低く提示してくるケースや、被害者が感情的に疲弊して提案を安易に受け入れてしまう場合などが挙げられます。
弁護士に依頼することで適切な金額を請求できるだけでなく、治療中からアドバイスを受けられたり、
加害者側保険会社とのやり取りを一任できたりと、ストレスを軽減することもできます。
保険会社の交渉に不安を感じる場合は、早めに相談することをおすすめします。
慰謝料が不当に低くなるケースとその回避法
もらい事故において、慰謝料が不当に低くなるケースは少なくありません。
その主な原因として、相手方の保険会社が自賠責基準や任意保険会社基準を用いて提示額を低く抑えようとする場合が挙げられます。
また、被害者が相場や計算方法を知らないまま安易に示談に応じてしまうことも、慰謝料が低くなる要因です。
これを防ぐためには、弁護士基準に基づいた適切な計算を行うことが鍵です。
弁護士基準を適用することで、適正な支払い金額を確保すると同時に、保険会社との交渉もスムーズに進めることができ、結果として損害賠償の増額が期待できます。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、弁護士基準に基づいた適切な請求に向けてサポートを行います。
もらい事故に遭い、ご自身が受け取れる慰謝料額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
 弁護士
弁護士